償却資産への課税
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものとされています。
償却資産の範囲
固定資産税の対象となる償却資産には6種類あり、具体的には次のようなものです。
1.構築物
舗装路面、店舗内装、養魚池、煙突、橋、貯水池、門塀、庭園、井戸、広告塔、キャノピーなど
【注意】家屋で評価されない建物(事業用)も構築物になります。
2.機械及び装置
工作機械、土工機械、印刷機械、食品加工製造機械、土木建設機械等、冷凍機、自動車製造設備、鉄鋼業設備、事務用機械製造設備、電気業用設備(太陽光発電設備等)など
3.船舶
ボート、漁船、遊覧船、貨物船など
4.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5.車両及び運搬具
大型特殊自動車(フォークリフト、ロードローラー、ショベルローダーなど)、構内運搬車など
【注意1】自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは含みません。
【注意2】農耕作業用自動車(農耕トラクター、刈取脱穀作業車、農業用薬剤散布車)のうち小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税の登録が必要であり、償却資産として申告の必要はありません。
6.工具、器具及び備品
事務机、椅子、キャビネット、陳列ケース、テレビ、ファクシミリ、カメラ、自動販売機、看板、金庫、時計、寝具、冷蔵庫、理容美容機器、医療機器、事務機器など
償却資産の申告
地方税法第383条の規定により、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産所在の市町村長に申告しなければなりません。
なお、虚偽の申告を行った場合は地方税法第385条による罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、不申告の場合は日田市税条例第75条による罰則(10万円以下の過料)の対象となる場合があります。
申告方法
毎年12月下旬頃に郵送でお送りしています申告書様式にて申告を行ってください。また、地方税ポータルシステム「eLTAX」でも申告を行うことができます。
償却資産申告書(様式) (Excelファイル: 213.5KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)様式 (Excelファイル: 91.5KB)
種類別明細書(減少資産用)様式 (Excelファイル: 84.0KB)
償却資産申告書 記載例 (PDFファイル: 316.6KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)記載例 (PDFファイル: 171.3KB)
申告の対象とならないもの
- 自動車税及び軽自動車税の課税客体である自動車
- 無形減価償却資産(漁業権、水利権、特許権など)
- 生物(ただし、観賞用・興業用及びこれらに準ずるものは申告の対象になります)
- たな卸資産(店などに陳列している商品など)
- 少額償却資産(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入するもの及び20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの)
- 用途廃止資産(現在使用されておらず、将来においても使用できないことが客観的に明確である資産)
注意事項
遊休、未稼働資産(一時的に稼動を停止又は休止しているもの及び事業の用に供することのできる状態にある資産)については、申告をする必要があります。また、一時的に休業されている所有者についても、申告をする必要があります。
地方税法第17条の5の規定により、調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、過去に遡って課税されます。
償却資産の評価方法
償却資産の評価は、前年中に取得された償却資産にあっては当該償却資産の取得価格を基準とし、前年前に取得された償却資産にあっては当該償却資産の前年度の評価額を基準とし、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価を考慮してその価格を求める方法によるとされています。
償却資産の評価の算定
- 前年中に取得された償却資産 評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
- 前年前に取得された償却資産 評価額=取得価額×(1-減価率)
【注意】評価額の最低限度は、当該償却資産の取得価額の100分の5です。
償却資産の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され税負担が軽減されます。該当資産をお持ちの方は、特例の対象となる資産の関係書類を添付のうえ申告書と共にご提出ください。
なお、課税標準の特例内容については、地方税法改正に伴い変更される場合がありますので、ご不明な点があれば税務課資産税係までお問い合わせください。
償却資産の申告における耐用年数
償却資産の申告における耐用年数については、「 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 」別表第1、第2、第5及び第6に掲げられた法定耐用年数によるものとされています。
耐用年数表は下記のファイルをご覧ください。
別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 (PDFファイル: 242.4KB)
別表第2 機械及び装置の耐用年数表 (PDFファイル: 99.2KB)
別表第5 公害防止用減価償却資産の耐用年数表 別表第6 開発研究用減価償却資産の耐用年数表 (PDFファイル: 39.4KB)
太陽光発電設備に関する申告
太陽光発電設備を設置した個人又は法人は、償却資産の課税の対象になることがあります。設置された太陽光発電設備の状況を確認の上、対象となる場合は申告をお願いします。
なお、太陽光発電設備を設置した場合、土地の課税地目が変更されることがあります。
太陽光発電設備の申告対象について
|
設置者 |
10kw以上の太陽光発電設 | 10kw未満の太陽光発電設 |
|
個人 (住宅用) |
発電量の全量または余剰を売電しない場合でも、発電するための事業用資産となり、課税対象となります。 |
発電するための事業用資産とはなりませんので、課税対象外です。 |
|
個人 (事業用) |
事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。 | |
| 法人 | 事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。 | |
申告対象であるかのご確認として、以下の判定フローチャートをご活用ください。
太陽光発電設備の固定資産税の区分について
| 太陽光 パネル |
架台 | 接続 ユニット |
パワーコンディショナー | 表示 ユニット |
電力量計等 | |
| 家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 償却 | ||||
| 架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | |||||
| 家屋以外の場所に設置 | 償却 | |||||
【家屋】家屋として家屋調査時に評価するため、償却資産としての申告は不要です。
【償却】償却資産に該当するため、償却資産としての申告が必要です。
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
取得時期によって適用対象が異なります。特例を受ける場合は、以下の必要書類をご提出ください。
| 取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~令和6年3月31日 |
| 対象設備 | 経済産業省による「固定価格買取制度の認定」を受けた再生可能エネルギー発電設備(10kw未満は除く) | 「固定価格買取制度の対象外設備」であって、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けた設備 |
| 必要書類 |
1.経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写) 2.電気事業者と締結している『特定契約書』 又は『電力受給契約書のご案内』(写) 3.太陽光発電設備図面 |
1.一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』(写) 2.太陽光発電設備図面 |
| 適用内容 | 3分の2に軽減 |
1,000kw未満の場合 3分の2に軽減 1,000kw以上の場合 4分の3に軽減 |
| 適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 | |
リース資産について
リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者となります。その場合は、リース会社に申告義務がありますので、税務課資産税係までお知らせください。
資料調査及び現地調査について
市税務課では、適正かつ公平な課税を行うための調査を実施しており、現在関係機関との情報連携を行い、太陽光発電設備の調査を強化しています。調査にあたっては、資料提供や現地確認を依頼することもありますので、ご理解ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









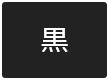
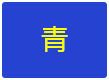
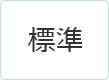
更新日:2024年11月07日