暑い季節の食中毒にご注意ください!
食中毒について
食中毒は、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。普段、当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を引き起こすことがあります。
家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず、重症化することもあります。食中毒が疑われる場合は、速やかに病院を受診しましょう。
食中毒注意報の発令状況
大分県では、夏季に多発する食中毒を未然に防止するため、気象状況が食中毒の発生しやすい条件に達したときに「食中毒注意報」を発令しています。
詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
食中毒予防の3原則
食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。
食中毒を予防するための3原則
- 細菌を食べ物に「つけない」
- 食べ物に付着した細菌を「増やさない」
- 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」
家庭でできる食中毒予防の6つのポイント
ポイント1 食品の購入
- 表示のある食品は、消費期限などを確認し、購入しましょう。
- 購入した食品は、肉汁や魚などの水分がもれないように、それぞれビニール袋などに分けて包んで持ち帰りましょう。
- 特に、生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理に必要な食品の購入は、買い物の最後にするよう心がけ、購入後は早めに帰るようにしましょう。
ポイント2 家庭での保存
- 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
- 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。めやすは、冷蔵庫や冷凍庫の7割程度です。
- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持することがめやすです。
- 肉や魚などは、ビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁などがかからないようにしましょう。
ポイント3 下準備
- 調理場や台所付近のゴミはこまめに捨てましょう。
- 調理器具が汚染されると、他の食品にも影響します。包丁、まな板、ふきんなどは洗って消毒し、清潔を保ちましょう。
- 冷凍食品を解凍する場合はなるべく冷蔵庫で行いましょう。
- 野菜はよく洗い、魚や肉と離して保管しましょう。
- 食中毒予防の基本は手洗いです。肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手を洗いましょう。
ポイント4 調理
- 台所は清潔にし、調理する前に手を洗いましょう。
- 加熱調理が必要な食品は、十分に加熱しましょう。めやすは、中心部の温度が75℃で1分間以上加熱することです。
- 料理を途中でやめてそのまま放置すると、細菌が食品についたり、増えたりする原因になります。
- 電子レンジを使う場合は、均一に加熱されるようにしましょう。
ポイント5 食事
- 食事の前には必ず手を洗いましょう。清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
- 調理後の食品を室温に長く放置しないようにしましょう。
ポイント6 残った食品
- 残った食品を扱う前にも手を洗いましょう。残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。
- 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けして保存しましょう。
- 温め直す時も十分に熱くなるまで加熱しましょう。
- 時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに思い切って捨てましょう。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 感染症対策係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(日田市役所6階)
電話番号:0973-22-8243(直通)
ファックス番号:0973-22-8315
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









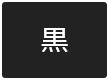
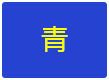
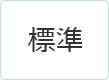
更新日:2025年06月26日