2024年人権コラム「心、豊かに」
「人権コラム 心、豊かに」は、「広報ひた」に掲載(毎月)しています。
「日本語」で大丈夫【1月1日号掲載】
1995(平成7)年に発生した阪神・淡路大震災のとき、日本で生活・滞在する多くの外国人が、日本語または英語を十分に理解できず、必要な情報が不足し、適切な行動につながらなかったというケースがありました。
このことを教訓とし、日本語が不慣れな外国人に、災害発生時、素早く的確に情報を伝えることを目的に考案されたのが「やさしい日本語」です。当初は、災害時の情報伝達手段として使われていましたが、今では、平時の活用においても研究され、行政情報や毎日のニュース発信など、全国の様々な分野で広がっています。
ある地方都市で暮らす外国人を対象とした調査では、「やさしい日本語」であれば理解できるという人は6割を超えることが分かりました。一方で、英語力を問う質問では、「英語ができる」と回答した外国人は、会話力で2割弱、読解力では2割強に留まり、英語に翻訳すれば、多くの外国人に伝わるといった考えは当てはまらないことが分かっています。
日本では、地震や風水害などは「いつでも起こりうる」という"意識"の備えを呼び掛けていますが、国によっては起こる災害が違い、また災害が起きたときの不安要素もそれぞれです。例えば、一定の安全を確保するために「避難所」を活用しますが、避難所が無料で誰でも入れる場所であることを知らない人もいるなど、日本人の感覚では気付かないこともあります。
2023(令和5)年11月30日現在、日田市で生活をする外国人は564人。「やさしい日本語で対応してくれる、やさしい日本人」がいることを多くの外国人が知っているはずです。「助け合いは必要だが、言葉が伝わらないだろう」というマイナスの先入観を持たず、簡単な言葉や短い文でゆっくり話し掛けてみてください。
「お客様は神様です」【2月1日号掲載】
「人前で歌うとき、あたかも神前で祈るときのように、雑念を払ってまっさらな澄み切った心にならなければ完璧な藝をお見せすることはできない。お客様を神様とみて歌う」。ただ、「お客様は神だから徹底的に大事にして媚びなさい。何をされようが我慢して尽くしなさいと発想、発言したことはまったくない」と、かの有名人は、表題(フレーズ)の真意を説明しています。
日本が誇る「おもてなしの文化」は、外国人にも強烈なインパクトを与えています。相手(顧客)に快適な時間を過ごしてもらうことの喜びを求めるという、自国にはない心遣いの文化に心を動かされ、日本のサービス現場で働くことを強く希望する外国人も少なくないようです。
ところが、この文化を過剰に受け止め、さらには自己の承認欲求を満たすため、暴言や暴行、脅迫、不当な要求に偏ってしまう「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が問題視され続け、沈静化の兆しは見えてきません。「度を超えた」行為は他の顧客への迷惑に止まらず、企業の経営の阻害、またそこで働く労働者の就業環境に不利益をもたらすなど、許すことのできないものとなっています。
カスハラが起こる要因は、「目の前で起こった出来事を迷惑行為に変えてしまう、受け手(顧客)の性質」という個人の内面的な課題とされており、その要因の解消はほぼ不可能と言えます。このため、悪質な行為を繰り返す客の宿泊を断ることが可能となった改正旅館業法の施行(令和5年12月13日)や、ある航空会社は運送規約を定めた約款を見直し、搭乗を拒否できる迷惑行為の明示の検討を始めるなど、各方面でカスハラを抑止する動きが始まっています。
「おもてなしの文化」がこの先も称賛を受けるために、その質を高めるための顧客の声は重要です。ただ、相手の非ばかりを取り上げて、迷惑行為によって自分の心の欲求を満たそうとする、そんな「神様」であってはいけません。
未来を紡ぐために【3月1日号掲載】
「ギャップ」。二つの事象や状態、期待と現実などの間に存在する「差異」を指す言葉。例えば、男女間で家事や育児などに対する意識や負担(責任)に差異がある"家事ギャップ"。また育児に関して、親世代や祖父母世代との考え方の差異を表す"子育て世代間ギャップ"などがあります。
"家事ギャップ"は、総務省が実施した「社会生活基本調査(令和3年)」で顕著に示されています。6歳未満の子を持つ世帯の1日の家事(育児・介護・看護なども含む)に費やす平均時間は、夫の1時間54分に対し、妻は7時間28分となっており、平成28年と比べると夫婦間の差は縮まっているものの、まだまだ相当の開きがあるようです。
この差をできるだけ縮め、どちらか一方に負担が偏ることのないよう、家事や育児、さらには仕事を含む暮らしの全般については、夫婦で対話し、知識などのギャップを埋める努力が大切です。その際には、内閣府が作成した「夫婦が本音で話せる魔法のシート/○○家作戦会議」を参考にするのもひとつの方法です。
共働き世帯の増加によって、祖父母が育児に参加する場面が多くなったことで、注目されるようになった"子育て世代間ギャップ"は、そのギャップに対する戸惑いから、トラブルに発展してしまうケースもあるようです。世代間で育児に関する考え方に差異があるのは当然なことかもしれませんが、昔と今の子育ての特徴をお互いに認知することは、ギャップの解消に役立つはずです。祖父母世代が親世代の子育てを応援し、親世代は祖父母世代から大きな協力を得るという相互作用により、子育てに「ゆとり」が生まれるという期待が持てます。
時代とともに生活環境や物ごとに対する価値観も激しく変わっていきます。家庭(家族間)でコミュニケーションを図り、お互いに尊重し価値観を共有することが、次世代を担う子どもたちの個性を伸ばし、穏やかな生活を送るための導きになるのではないでしょうか。
相手の役に立つ「心配り」【4月号掲載】
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「推進法」)」の改正法が施行され(令和6年4月1日)、事業者にも「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
日常生活における合理的配慮とは、「道理にかなっている状態の上で、良い結果となるように、あれこれと心を配ること」ですが、推進法では、「障がいを持つ人と持たない人が、同じく平等な社会生活を送れるよう、社会的障壁を排除すること」と位置付けられています。
推進法では「障がいを理由とする差別」を1.不当な差別的取扱い 2.合理的配慮を提供しないの2つに分けて考えています。1.は、(正当な理由がなく)「入店や入居の拒否」、「商品やサービスの制限」など、障がい者の権利利益を侵害することです。2.は、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、ア)負担になりすぎない範囲 イ)社会的障壁を取り除くために必要で合理的であるにもかかわらず配慮しないことです。車いすの利用者が段差の前で困っているときに、「スロープを出す」、「手伝う」などの行為を提供しない、聴覚に障がいのある人が筆談を求めても応じないなどの行為が当てはまります(経済産業省の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例が記載されています)。
「合理的配慮の提供」は誤解されやすく、" 思いやり"と受け止めてしまう傾向がありますが、少し異なります。例えば、垂直に移動するためには、誰もが階段が必要であるように、障がいのある人が感じる障壁を取り除く行為が「合理的配慮の提供」であって、これは誰もが当たり前に持っている権利を侵さないという基本的な考えが前提となっています。
推進法では、合理的配慮の提供に際して、過重な負担や優遇を求めているものではありません。求められていることは、全ての人が尊重され、お互いに理解し合う共生社会の実現に必要な「心配り」です。
相手の役に立つ「心配り」 (PDFファイル: 76.5KB)
「平凡」という幸せ【5月号掲載】
2006(平成18)年、福岡で発生した飲酒運転による凄惨な事故。加害者(犯人)は、3人の幼い命を奪う事故を起こしたにも関わらず、仲間と共に飲酒の証拠隠滅を図るなど、「人の命」を軽んじる行動をとりました。
この事件を契機として、飲酒運転に対する罰則が強化されることになりましたが、今もなお各地で飲酒運転による交通事故は後を絶ちません。この悪しき状況は、飲酒運転や危険運転などが明らかな犯罪行為であること、そしてその犯罪によって被害者とその家族が、身体的被害や財産的被害に止(とど)まらず、様々な被害に苦しめられていることについて、認識と理解が深まっていないことが要因の一つにあるようです。
交通犯罪に限らず、暴行や傷害、性犯罪など、犯罪による被害を受けた人やその家族を苦しめるのは、犯罪そのものやその後遺症だけではありません。興味本位の噂、心ない中傷や偏見による人権侵害、また過熱報道によるプライバシーの侵害などの「二次的被害」に苦しめられる被害者も多く存在します。
このように、立ち直るきっかけさえもつかめず、孤立してしまう被害者の救済措置と適切な支援に対する社会的な関心が高まり、犯罪被害者等の権利や利益の保護を図るため、平成17年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。これによって、犯罪被害者等の人権を守る必要性が大きく取り上げられるようになり、犯罪被害者等が地域で安心して暮らせるよう、当事者の心に寄り添い社会全体で支えていくための施策の推進が図られています。
犯罪によって失われるのは、被害者の命だけではありません。加害者も人生の多くを失い、誰かの支えがなければ生きていけなくなります。
"行ってきます"
いつものように元気に出掛けた家族の"ただいま"を聞くという「平凡」がいかに大切であるかを見つめ直すことが、犯罪と犯罪による被害者の苦しみをなくしていくことになるはずです。
「する側」と「される側」の心合わせ【6月号掲載】
「カミングアウト」。
誰にも打ち明けていなかった自分の秘密を自ら誰かに話すことで、その多くは「自分がセクシュアルマイノリティであることを打ち明ける」という意味で使われています。
これに対して「アウティング」は、当事者が公表していない個人情報(例えば、性的指向や性自認など)を当事者の了解を得ることなく、第三者に暴露する行為として使用されています。
この「アウティング」は、口頭によるものに限定されず、インターネット上などで不特定多数の人に情報を流す行為も該当します。仮に、これらの行為が「当事者の気持ちを察した」ものであっても、秘密の暴露は当事者を精神的に追い込んでしまう可能性があります。
2015(平成27)年、ある大学院の学生が同性愛者であることを同級生に暴露され、大学の敷地内で転落死するという事件が起きました。この事件の裁判で、アウティングは「人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであり、許されない行為であることは明らか」と言及されたこともあり、アウティングが世間から注目されるようになりました。また昨年には、アウティングによって、精神疾患を発症し、労働基準監督署から労災として認定される事案も発生しています。この事案は職場内における緊急連絡先を登録の際に、同性パートナーの存在を会社側に(一定の条件を付して)伝えたところ、そのことを広く暴露されたものです。アウティングされた当人は、会社に対する信頼が失せ、仲間との関係性も悪化し、退社を余儀なくされることとなってしまいました。
アウティングは「される側」の居場所を奪うばかりか、精神的な苦痛を与え、さらには重大な人権侵害につながってしまうという認識の広がりが求められています。カミングアウトされたときには、「する側」の思いの尊重と「伝えてよい範囲」の確認をし、多様性を認め合う社会の一員になるよう心掛けることが大切です。
「する側」と「される側」の心合わせ (PDFファイル: 84.2KB)
見過ごせない「内輪の問題」【7月号掲載】
DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する専門機関への相談件数は、2020年度をピークに高水準で推移しています。2023年度の内閣府調査では、結婚経験のある人の約4人に1人がDV被害を受けており、その大半は「女性」です。
DVに明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった人から振るわれる暴力」という意味で多く使用されます。
DVには、身体的暴力(殴る、蹴る)、精神的暴力(無視する)、経済的暴力(生活費を渡さない)、さらには子どもを巻き込んだ暴力などがあり、「夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がない」とする古い社会通念や「妻に収入がない」という男女間の経済的格差など、当事者の問題として片付けられない構造的な問題が大きく関係しています。
その上で、「多少の度を越えた夫婦喧嘩」、「他人が関与すべきではない内輪の問題」などとする周囲の軽視や遠慮によって、問題の長期化と被害を受ける側の孤立を招いています。
DVの加害者は暴力によって相手をコントロールし、支配しようとします。被害者はその暴力によって、その後の人生において身体にも心にも大きな傷を負ってしまいます。また家庭内で起こることが多い配偶者等からの暴力は、子どもにも深刻な影響を与え、時に「暴力の世代間連鎖」をも生み出してしまいます。
「自分さえ我慢すればいい」、「自分が悪いから暴力を振るわれる」という自己否定に、日本特有の「家庭は私的領域」という考えがプラスされ深刻化するDVは、被害者のみの努力や行動では容易に解決できる問題ではありません。周囲が当事者のSOSに気付き、一歩踏み込んだ対応をとることが、当事者を救う大きな原動力になるのではないでしょうか。
見過ごせない「内輪の問題」 (PDFファイル: 88.3KB)
新5,000円札(情熱とともに)【8月号掲載】
2004年以来、20年ぶりに新紙幣が発行されました。新たな紙幣にデザインされたのは、
1.10,000円札
「近代日本経済の父」と呼ばれる渋沢栄一
2.5,000円札
日本で最初の女子留学生としてアメリカに渡った津田梅子
3.1,000円札
破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎
5,000円札の顔となった津田塾大学の創設者である津田梅子は、女性活躍の先駆者として必ずと言って良いほど名前が挙がる人物です。女性の地位向上が日本の発展につながるという信念に基づき、「男性と協同を図り、対等に力を発揮できる女性」を育成するため、女性の高等教育に生涯を捧げました。
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保などを推し進める「男女共同参画社会基本法(1999年)」の制定以降、様々な取組が進められてきましたが、社会情勢の変化等によって新たな課題も生じています。
例えば「仕事・職場」の分野では、管理ポストを占める女性の割合や男女間の賃金格差など、解消されなければならないことが思うように進んでいません。また、昨今では性的マイノリティ(少数者)に対する職場の対応に差別的な言動が見られるなど、「対等」に至っていない状況が作り出されています。
津田梅子はアメリカで学び帰国した際、「女性を必要としない日本社会に落胆」し、女性教育の必要性を痛感しました。その上で、「何かを始めることはやさしいが、それを継続することは難しい。成功させることはなお難しい。」という言葉を残しています。
明治の時代に「男女の共同(協同)」に着眼した梅子を描いた真っ新な5,000円札が令和の時代に登場することになりました。新紙幣の流通とともに、梅子の捧げた情熱が世に広がることを期待します。
新5,000円札(情熱とともに) (PDFファイル: 90.9KB)
「助けて」が届く社会【9月号掲載】
東日本大震災(2011年)の発生から約6年後に内閣府が実施した世論調査では、「避難生活の長期化によるストレスに伴ういさかいや虐待(61.4%)」、「学校、幼稚園等で嫌がらせやいじめを受ける(58.9%)」、「差別的な言動を受ける(40.2%)」、「職場で嫌がらせやいじめを受ける(29.6%)」などが、「被災者が受けていると思われる人権問題」として挙げられています。
国立研究開発法人の情報通信研究機構(NICT)は、今年1月1日に発生した能登半島地震の発生後から24時間にSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の交流サイトに「日本語で投稿された救助要請」を分析しました。その結果、投稿の約1割が「デマ(うそ)」であったことが判明したと発表しています。
2016年の熊本地震発生後の同じような救助要請では、投稿数573件のうち、デマがわずか1件であったことと比較すると、SNSを利用した妨害行為と人権侵害が急増していることが分かります。この状況の背景には、注目や関心が集まる投稿によって閲覧数を稼ぎ、自分自身の収入を増やすといった「アテンション・エコノミー(関心経済)」を優先する意識の広がりがあるようです。
地震や台風、大雨などの災害が全国各地で発生する中、SNSは貴重な情報発信の手段として活用が重要視されています。その上で、正確な情報を流すことは、迅速かつ効率的な救助活動につながります。
災害(非常)時は、誰もが自分のことで精一杯になり、不安に襲われます。他者の関心を引き、利益を追求するような行動は、本当に救助を必要とする人に対する支援が妨げられるなど、命に関わる問題を引き起こしてしまいます。
冒頭の東日本大震災後の調査では想定されなかった、「SNSを利用する人権侵害」を食い止め、「助けて」という声が、誰にも邪魔されず確実に届く社会を一刻も早く取り戻さなければなりません。
見るべきは「その人自身」【10月号掲載】
「どうして、そんなことを尋ねられるのだろう?合否に関係あるのかな?」
日本労働組合総連合会(連合)が実施した就職差別に関する調査(2023年)によると、「本籍地や出生地に関する質問(43.6%)」、「家族に関する質問(37.2%)」など、就職(採用の合否)とは無関係と思える「答え」を多くの企業が求めていることが分かりました。
人生の岐路とも言える就職の場面で、「この企業で働きたい」という真摯な意欲に応えるとき、「求めている資格、技術、度量などが足りなかった」などの努力で改善できる理由ではなく、出身地や家族構成を合否の決定の理由とすることは、差別や排除の意識に準じた理不尽な対応です。
このように、「身元を調べようとする」動きは未だに根強く残っています。調査会社などを頼り、他人の出自などを勝手に調査し、結婚や就職の際に利用する重大な人権侵害とも言える身元調査が依然として後を絶ちません。
2011(平成23)年、東京都内の法律事務所が、全国各地の探偵社や調査会社からの依頼を受け、「大量」の戸籍謄本等の不正取得を繰り返した事件が発生しました。また、大分県内でも委任状の偽造による同様の事件が起きています。
この大分県内の事件は、「本人通知制度」への登録によって不正が明らかになり、差別の拡大と個人情報の流出を防ぐことにつながりました。この制度は、身元を調べようとする動きに対抗する手段として大きな効力があるため、登録者を増やすことで、「不要な身元調査(差別)を許さない」という風土が作られます。
超高齢化社会や働き手(若者)の減少によって、日常社会の様々な場面で、これまでとは違う対応による社会基盤の形成が求められています。このような状況下にあって、出自にこだわり「他者の人生の合否」を決める必要はありません。
見るべきは「その人自身」 (PDFファイル: 87.1KB)
あなたにもできる189(いちはやく)【11月号掲載】
近隣から聞こえる怒鳴り声と子どもの泣く声。「心配だけど、どうしたら良いのか…。」
社会を取り巻く環境の変化が、「こどもの人権」を脅かしています。周りには見えにくい、いじめや体罰、性被害、また家庭でも起こりうる"児童虐待"は、深刻さを増しています。
大分県の児童相談所に寄せられた虐待に係る相談件数は、2023(令和5)年度には、1,852件となり統計の開始以降、過去最多の件数を記録しました。
言葉による脅しや子どもの面前で家族に暴力を振るうといった「心理的虐待」が半数(958件)以上を占め、次いで、殴る・蹴る・叩くなどの「身体的虐待」もかなりの件数(600件)となっています。過去最多の相談件数となった背景には、各地で児童虐待の事件が相次ぐことを受け、「虐待を早期に発見しよう」という意識の高まりが要因のひとつとなっていることが考えられます。それでも、表面化しづらい家庭内暴力が、依然として多く起きているという実態は変わりません。
「こども家庭庁」は児童虐待の防止対策として様々な取組を進めています。なかでも児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は、虐待と思われる場面に遭遇した人からの、迅速な情報提供や相談によって、「虐待を止める、防ぐ」役割を果たしています。
社会構造の移り変わりは、利便性をもたらした反面、地域のコミュニティ能力を削いでしまう状況を作り出そうとしています。小さな命のひとつひとつを保護者だけでなく地域全体、社会全体で見守ることが、今の日本社会には求められています。
「虐待かもしれないけど確信が持てない」、「間違いだったらどうしよう」という懸念やためらいを捨てた勇気ある行動で救われる子どもがいます。
一歩踏み出し、行動してみませんか。
あなたにもできる189(いちはやく) (PDFファイル: 79.3KB)
無意識の「自覚」【12月号掲載】
「ピンクは女の子の色だから好きと言えなかった」、「消防士さんになりたいという夢を語れなかった」。
そんな経験をしたこと、耳にしたことはありませんか?
「男らしさ、女らしさ」を基に男女の役割を決めつけてしまうこと、性別の違いに対し思い込みや偏見を無意識に持つことを指す「ジェンダーバイアス」。
幼児期からの成長過程において、家庭や学校などで様々な文化的・社会的な規範にさらされると同時に、偏った見方や思い込みにつながる情報に触れ、無意識に形成されるものです。
冒頭にあるような、色や職業に対するイメージはジェンダーバイアスの典型例ですが、「女性実業家」、「料理男子」など、ことさらに性を強調しようとする表現の根っこには、性別による役割をイメージした固定的な思い込みが見え隠れしています。
「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標の5番目には、"ジェンダー平等を実現しよう"と掲げられていますが、ジェンダーバイアスによる影響は多く、例えば女性議員や女性管理職の不足や男女間における賃金格差などは世界中で注目されています。
また、個人のスキルアップや飛躍の可能性を阻み、社会全体の発展を妨げてしまう危険性があり、特に途上国では、ジェンダーバイアスによって教育や就労の機会が奪われることもあります。
ジェンダーバイアス(無意識のイメージ)を払拭するための第一歩は、まず自分自身の心の中の確認です。
そして、これまでの自分の行動が、「自分や誰か」を一定の枠にはめるようなものではなかったか、また誰もが同じように抱えている「単純な思い込み」として片付けてしまうことがなかったかを振り返り、「無意識を意識した行動」に変えていくことです。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 人権・部落差別解消推進課 啓発推進係(人権啓発センター)
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館1階)
電話番号:0973-22-8017(直通)
ファックス番号:0973-22-8259
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









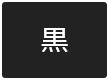
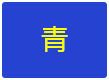
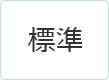
更新日:2025年01月08日