2025年人権コラム「心、豊かに」
「人権コラム 心、豊かに」は、「広報ひた」に掲載(毎月)しています。
「トゲ」のない距離【12月号掲載】
「寒い冬の日、ヤマアラシは暖を取るため互いの身体を寄せ合いますが、互いのトゲで傷つけ合ってしまいます。「離れてしまうと寒さに耐え切れず、近づけば傷つく」という葛藤に苦しむヤマアラシは、近づいたり離れたりを繰り返し、ついには互いを傷つけず、暖め合うことができる距離を発見し、「調和」を見い出します。
外敵から身を守るため身体に無数のトゲを持つ「ヤマアラシ」。哲学者ショーペンハウアーの寓話(ぐうわ)に出てくる出来事をアメリカの精神分析医ベラックが「ヤマアラシのジレンマ(ヤマアラシ症候群)」と名付け、人間社会の関係性のあり方になぞらえています。
常に誰かに評価され、ときには批判を受ける風潮の中では、自分を守るために「ヤマアラシ症候群」に陥りやすくなるという指摘があります。コミュニケーションを図ろうとするが、それが上手くいかず、他人から攻撃される(傷つけられる)ことを極度に恐れ、傷つく前に自分を守るため、先に相手を攻撃したり排斥したりし、結果として周囲から孤立してしまうといった実態がその一例です。
そもそも、他者との良好な(信頼できる)関係を築くためには一定のリスクがあることを承知し、他者を尊重し傷つけないような心構えが必要であることを認識しておかなければいけません。
そのうえで、互いに適度な距離を保つことが、「共存体制」を持続させるカギとなります。例えば、言論の自由という基本的人権は、自分の意見を表明する権利が保証されたものですが、その一方で、自分の意見が他者を傷つける可能性があることから、「自由」に係る取り扱いは多くの場面で問題視されています。
他者の人権を尊重するにあたっては、自分の選択や行動が人間関係に与える影響について、理解を深めることが大切です。自分自身の権利を守ると同時に、全体の「調和」を図ることが、真の人権社会の実現につながるのではないでしょうか。
日本初開催!「デフリンピック」を楽しもう【11月号掲載】
身体障害者を対象とした世界最高峰の障害者スポーツの総合競技大会とされるパラリンピックの始まりは1960年。そのパラリンピックよりも先に始まった「デフリンピック」。
「耳が聞こえない」という意味の「デフ(Derf)」とオリンピックが合わさったデフリンピックは、「きこえない、きこえにくいアスリート」のための国際的なスポーツ大会で、4年に1度(夏期と冬季)開催されています。大会の歴史は古く、初めての大会は1924年のパリ大会。今年100周年の節目を迎え、日本(東京を中心に)で25回目の夏季大会が開催されます。
競技種目は、夏季が21競技で冬季は7競技。ルールはオリンピックとほとんど同じですが、スタートや審判の合図は「旗や光、ジェスチャー」など、視覚で判別されるものが用いられます。また、手話やアイコンタクトによって選手間のコミュニケーションがとられるなどの工夫により、アスリートが競技に臨む環境が整備されています。
デフリンピックは、聴覚に障がいのある人がスポーツを親しみ、かつ自己実現を図るための機会を提供するとともに、デフスポーツへの理解を広げる役割を担うなど、共生社会を実現するための発展に寄与してきました。このため、今回の大会では「すべての人が輝くインクルーシブな街・東京の実現の貢献」をめざすとともに、応援アンバサダーの登用や手話単語を簡単に学べる動画を制作するなど、「みんなで大会を盛り上げる」ための準備が着々と進められています。
デフリンピックやパラリンピックは、スポーツが持つ魅力によって、あらゆる人の可能性を広げ、社会との架け橋になる貴重なイベントです。日本で開催されるこのイベントに触れ、熱い声援を送ることも共生社会の実現への大きな貢献となります。
日本初開催!「デフリンピック」を楽しもう (PDFファイル: 216.8KB)
「いただきます」を守る【10月号掲載】
食事を始めるときの挨拶として使われる、「いただきます」。この言葉は、単なる挨拶にとどまらず、私たちの命や人権に深く入り込んでいるものです。
「いただきます」には、食材の提供元となる自然や生き物、そして、それを手間暇かけて育てる、または調理する人に対する感謝の気持ちが込められており、食材の「命をいただく」行為に対する一種の儀式とも言えます。
世界人権宣言において認められている「食料への権利」。これは、すべての人が尊厳を持って、必要な栄養を満たす十分な食料を、継続的に得られる権利であり、飢餓や栄養不足から解放され、健康で文化的な生活を送るために不可欠な基本的な人権のひとつです。
ただ、承知のように世界には食糧危機や栄養失調に苦しむ人々が存在します。このような悲しい現実を考えると、「いただきます」という言葉には、目の前に並べられた食事(食材)のルーツや経路、そこに携わった人、そして誰もが有する食の権利などを意識させる社会的なメッセージが含まれていると言えます。
また、食材の選び方にも命を大切にする姿勢が深い関わりを持ちます。一例を挙げると、フェアトレード(発展途上国で作られた農産物や製品を適正な価格で継続的に購入することで、生産者の生活向上と自立を支援する貿易の仕組み)製品の選択は、農作物を育てる側の労働環境や生活を守る一助となります。
このように「いただきます」という言葉には、命・人権という重要なテーマが凝縮されています。食事が命の源であり、その背後には多くの人の努力や自然の恵みがあることを常に胸に留めておくことが大切です。
食事には「生命」が関わっています。「いただきます」を自分自身だけでなく、他者の権利や環境に配慮した意思表示として守り続けなければなりません。
「いただきます」を守る (PDFファイル: 305.6KB)
ハラスメント・シリーズ3.「人としての敬意」【9月号掲載】
前回、前々回では、「職場のパワハラ」にスポットを当てましたが、就職活動中の学生が被害を受ける「就活ハラスメント」も大きく注目されています。
その中でも、真っ先に挙げられるのは「就活セクハラ」。令和6年の調査では、対象となる学生の約3割が就活中にセクハラを受けたとされています。内容としては、「性的な冗談やからかい」「食事やデートへの執ような誘い」といった、職場内セクハラと同類のものが多くなっています。
企業にとっては、優秀な人材の採用という重要な場面であり、しかも相手はまだ自社の一員ではない学生であるにもかかわらず、試験(面接)の場でも「職場という狭い範囲が世界のすべて」であるような、身勝手かつあさましい振る舞いが露呈されているようです。
このような状況を受け、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の三省が合同で、毎年4月に公表する就職・採用活動に関する要請等では、ハラスメントの防止に関する要請が年々具体化しています。そして、その要請の中には当然のように、パワハラの防止が明記されています。就活中のパワハラ事例を見ると、面接時に「人格を否定するような暴言、受験者の家族をバカにした発言」などが挙げられており、評価の場である面接が受験者の人格をひどく傷つける場に変わってしまっているようです。そのうえで、面接官、採用担当者、役員など、評価の最前線役による人物の加害行為が多くなっています。このため、被害を受けた学生の4割が当該の企業に対し悪いイメージを持ち、さらには内定を辞退したケースも3割近くにのぼるなど、少なくない影響が表れています。
これまでに経験したことのないような「働き手不足」に直面している日本社会。働くことに希望を持つ学生は、ほとんどの場合が"ひとり"で試験(面接)に臨みます。その学生に対し、複数の人員で対応する企業側に「人権を尊重した配慮、相手に対するリスペクト」が欠如し、まっとうな就活ができないような現状を変えることも"待ったなし"の状態です。
ハラスメント・シリーズ3.「人としての敬意」 (PDFファイル: 220.2KB)
ハラスメント・シリーズ2.「職場の姿は」【8月号掲載】
パワハラには「わかりにくい=認めにくい」性質があります。例えば、職場で上司によるあからさまなセクハラ行為があったとき、それを見た周囲は「セクハラだ、見過ごせない」といった感情を抱き、"その行為の証人"となり得ます。ところがパワハラの場合、セクハラと同様の感情は抱いても、"その行為の証人とならない"ことが多々あり得ます。
シリーズ1.の広報ひた7月号でも書き記したように、職場でパワハラに該当する事案が起きても、「同じ失敗ばかり、注意されて当然」「言い回しはきついが、指導の範囲内だ」など、加害側を擁護してしまう空気感は少なからず発生します。そして、この空気感を構成する成分のひとつが、"トップや上司を敵に回せない = 怖い=自分は巻き込まれたくない"という「自己防衛機能」です。
職場(組織)の健全化を図るため、「ハラスメント防止委員会」などの自浄機能を整備する行政機関や企業は増えていますが、その委員会の構成メンバーは「内部の者」が主流で、「外部の者」の参画はほんの少数です。このため、内部の者がその組織の有力者の行為に対し、「パワハラだ。厳粛に処分が必要!」と踏み込めず、結果としてパワハラと認定されないまま改善されない状態が続いてしまう現実が多く見受けられます。このように、勇気を出して立ち向かおうとしても跳ね返される高いカベがパワハラを無くせない大きな要因となっています。
そこで、組織におけるパワハラを無くすためにやらなければいけないことのひとつに、ハラスメントを調査・審議する機関のメンバー構成を「外部の者(第三者委員会)」とすることです。某テレビ局もこの体制で事実と真実を探りました。
"職場のあなたの振る舞いをあなたの家族や友人、そして外部の人に教えても大丈夫ですか?"
外部への調査依頼は人選も含め、それなりの時間と経費が発生します。自分の所業が外部に知れわたり、しかも不要なお金が掛かるという状態は、組織にとって何ら利益をもたらさないことを共有・認識し、「職場という閉ざされた空間なら、権力に任せ何をやっても大丈夫。自分の人生に影響はない」などの都合の良い自己解釈を許さない風土づくりが急がれています。 次号に続く
ハラスメント・シリーズ2.「職場の姿は」 (PDFファイル: 332.2KB)
ハラスメント・シリーズ1.「本質を見て」【7月号掲載】
「お前らの脳みそは鳩の脳みそより小さい」「最上級のあんぽんたん」「三流大学以下」。これは、ある自治体のトップが職員に向けて発した言葉です。このトップは「期待した提案や回答がなく、がっかりした気持ちの表現や叱咤激励だった」と言い訳していますが、ほかにも「育休を1年取ったら許さない」「いつ降格してくれるの」などのハラスメント発言もあり、そのすべてにおいて弁解、弁明を連発しています。
パワハラやセクハラが疑われたとき、加害側が発する言葉に「そんなつもりはなかった。指導の範囲、コミュニケーションのつもり」などがよく使われます。潔く非を認め、反省の意を表し被害側への謝罪などがあれば、たとえ許されない行為であったとしても被害側の心情も変わり、改善へとつながっていくはずなのですが。
厚労省によるパワハラの定義を要約すると、
- 地位、人間関係などの優位性を背景とする言動
- 業務上必要な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境を害する言動(1~3をすべて満たす)
とされており、そのうえで「判断基準」として、
- 言動の目的が、職員(社員)の育成か、それとも嫌悪の感情や退職に追い込むものか
- 言動の内容が業務の改善のために合理的か
- 言動の内容に被害側に対する人格的な攻撃を含むか
などが示されています。
冒頭の事例のように、職場(組織)のトップや上司によるパワハラがあったとき、
- 声を上げにくい、報復が怖い(恐怖感)ため、泣き寝入り状態が続く
- 声を上げたとしても組織の中に、パワハラを調査・審議する体制が整備されていない
- 体制が整備されていても、前出のような判断基準の精査など、パワハラの認定には時間を要する
などの理由から、被害側が休職や退職を選んでしまう「最悪な」状況になることがあるようです。
そのうえで厄介なのは、「まずは自分を見直せ」「多少の行き過ぎた言動をいちいちパワハラと言っていたらキリがない」など、被害側を責め、加害側を擁護する第三者の発言(意見)が聞こえてくることです。パワハラの本質を直視しない風潮は、日本社会の経済活動の停滞を招く危険性を含んでいます。
次号に続く
ハラスメント・シリーズ1.「本質を見て」 (PDFファイル: 348.3KB)
家族・幸せの「カタチ」【6月号掲載】
テレビは時代を映す鏡とも言われます。ドラマやアニメをはじめ、CMにそれぞれの時代を反映する代表的なものがあります。
日曜日の夕方に放映されている、サカナの名前が飛び交う家族のアニメがあります。このアニメの放映が開始されたのは1969年、高度経済成長の真っただ中。描かれる家族は、主人公の女性とその配偶者と子ども、そして主人公の親兄弟の総勢7人。厳格そうな父親を家長とし、主人公とその母親は家事に専念し夫を支えるというホームドラマが描かれ、当時の日本の家族の「カタチ」が映し出されています。
少し時は流れ1979年、22世紀から20世紀に舞い降りた猫型ロボットが主人公のアニメがテレビに登場。主人公は夫婦とその子どもの家庭に居候し、未来の道具でその子どもを助けます。
日本が高度経済成長期からバブル期を迎えようとする中で、家族の「カタチ」も大家族から核家族へとそのカタチを変えていきます。その中で、この2つのアニメに共通することは、どんなトラブルがあっても最後は笑い声があがる幸せな「カタチ」があることです。
さらに時は流れ令和の現代。家族を中心に置いたドラマやアニメは少なくなった気がします。その背景には、様々な家族や幸せの「カタチ」が増えてきたからではないでしょうか。
多様性を認め合う現代は、一人ひとりの家族や幸せの「カタチ」が尊重されるようになりました。同性パートナーや夫婦別姓など多様なライフスタイルは、今よりもっと増えてくるかもしれません。
憲法13条には「個人の尊重と幸福追求の権利」が規定されています。固定的な家族観にとらわれるのではなく「個人が望む幸福=幸せのカタチ」が実現できる時代となりました。そして、猫型ロボットが暮らす22世紀は、それが当たり前の時代になっているのかもしれません。
家族・幸せの「カタチ」 (PDFファイル: 301.0KB)
行動する勇気【5月号掲載】
ハラスメント、人権侵害、差別。
このような場面に遭遇し、「何とかしてあげたい。被害側を助けたい」という気持ちはあっても身体が動かない、適切な言葉を掛けられないなど、何も出来ない自分自身を悔やんでしまったことはありませんか。
そんな経験をもとに差別の抑止力として、注目されているのが「アクティブ・バイスタンダー」。バイスタンダーとは、医療用語では応急処置や心肺蘇生といった、救助に携わった第三者のことを指しますが、ハラスメントや暴力、差別の場面では「その現場に居合わせた第三者」という意味で使われています。
このような場面で、何らかの被害を受けている(受けそうな)ときに、第三者(傍にいる人)が介入(行動)することで、事態を悪化させない(予防する)といった効果があり、アクティブ・バイスタンダーは、直訳すると「行動する第三者」となります。
アクティブ・バイスタンダーとしてできる5つの介入方法は、1.注意をそらす(関係のない話などで、加害側の言動を邪魔する)2.周囲に助けを求める3.証拠を残す(写真や動画など。ただし、取り扱いには注意)4.事案後の対応(被害側への声掛けなど、フォローやサポートを申し出る)5.直接介入(加害側への注意、指導)があります。
ただ、状況によっては危険が伴うことがあるため、まずは自分自身の安全の確保が先決です。また、加害側の主張を支持するような「誤った行動」によって、被害側に罪悪感や無力感を生じさせ、孤立させるなど、深刻化を招かない対応を心掛けることが必要です。
差別やハラスメント、暴力は当事者だけの問題ではなく、周囲が「自分自身の問題」と捉えることで変えられることもあります。 アクティブ・バイスタンダーが増えることで、被害側が声を上げやすい社会につながることは間違いありません。
無理なくできることからやってみませんか。
おたがいさまの一言【4月号掲載】
「ダブルケア」。
子育てと介護の両立状態を指し、このダブルケアに直面し苦悩する「ダブルケアラー」と呼ばれる人が増えています。
ダブルケアラーが増えている理由として、真っ先に挙げられるのが、晩婚化と出産年齢の高齢化です。第一子を出産する年齢が上がったため、子育てが落ち着いてから始まっていたとされる介護が、子育てと重なるようになり、10年以上にわたりダブルケア状態が続く例もあるようです。
このダブルケアには問題とされていることがいくつかありますが、中でも大きな負担として問題視されているのが育児費用や介護費用といった「経済的な負担」、また周囲からの理解が得られないために孤立してしまう「精神的な負担」などが挙げられます。
2016年に発表された内閣府の調査によると、日本のダブルケア人口は約25万人。ただ、この調査は「育児=小学生以下」、「介護=親・祖父母(義理を含む)」と対象を限定していたため、「子育て」を高校生までと捉え、また「介護」に兄弟姉妹を加えれば、ダブルケア人口は25万人を大きく超えると推測されています。
団塊の世代の高齢化によって、国民のおよそ5人に1人が後期高齢者(75歳以上)となる2025年問題に差し掛かり、その後の2040年には、団塊ジュニア世代が高齢期を迎え、現役世代の急減が危惧されています。併せて、高齢者が高齢者のケアを担う「老老介護」、子どもが介護を担う「ヤングケアラー」、そして文中の「ダブルケア」など、ケアに関する様々な問題はすでに表面化しています。
日本社会の健全な基盤の創造のため、誰もがケアの当事者となる可能性があることを認識することが大切です。そして、「特定の人のみ」に重い負担がかかってしまうことのないよう、家族や親族との協力はもちろん、近隣の人や職場の理解を深め「おたがいさま」の関係を構築していくことが求められています。
その投稿“待った”【3月号掲載】
「匿名ならば大丈夫。誰の仕業か分からないし」。こういった無責任かつ自己中心的な意識のもとに、他者の誹謗中傷や差別的な表現をインターネット上に書き込むことは許されないものです。悪質なものに対しては、(それが一度だけであっても)発信者の特定と責任の追及がなされ、場合によっては大きな代償を伴うこととなります。
誹謗中傷が要因となり、自死を選んでしまうような悲劇が起こるなど、ネット上の「問題投稿」の流通は深刻さを極めています。ただ、ネット上でそのような投稿を見つけても、「消す方法が分からない。そもそも消せるものなのか」など、「削除」については「社会的課題」として議論が続けられてきました。
こうした中、「情報流通プラットフォーム対処法(通称)」が令和6年5月に可決・公布され、1年を超えない範囲内で施行されることとなりました。この法律では、大規模なプラットフォーム事業者(ネットを管理運営する企業等)に対し、削除対応の迅速化を図るため、「申出窓口を含む申出に対する体制の整備と申出に対する判断・通知」、また運用状況を透明化するため、「削除基準の策定と削除した場合の発信者への通知」などを義務付けています。
要約すると、削除を申請した投稿の「消える(消す)」または「消えない(消せない)」の結果が申出人に伝えられ、「消える(消す)」場合は、これまでよりもスピーディーに実行されるというものです。
しかしながら、法律の整備によって問題の根本が解決されるものではありません。問題投稿(人権侵害)の根絶には「1.他者の誹謗中傷や差別的な書き込みはしない2.不確かな情報や他者のプライバシーに触れる情報を書き込まない3.書き込みが不特定多数の人に見られる可能性がある」という意識と認識を持つことが大切です。
情報に対する接し方、考え方を大きく問う社会環境の形成が始まっています。全ての人が、生きていく上で情報を必要不可欠なものとして「大切に扱う」ことが求められています。
つながる思い【2月号掲載】
素敵だなあと思って買った品物。その品物の製造から販売までの過程で、「人権が侵害」されていたら、どう思いますか。
セクハラやパワハラなど、企業活動において発生する様々な「人権問題」。こうした問題への対応は、時として企業の価値に大きな影響を与えます。2020年、政府が「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を策定。その後の2022年には、企業における人権尊重の取組を後押しするため、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を整備しています。
サプライチェーンとは、商品や製品が消費者の手元に届くまでの1.材料調達2.製造3.輸送・配送4.販売5.消費といった一連の流れのことです。この流れの中で、実際に起こった(または起こり得る)人権問題として、1.材料生産現場の児童労働のリスク2.製造現場における外国人労働者への差別3.トラック運転手の長時間労働4.販売店の労働環境の悪化、商品広告の差別的表現5.消費者の健康や安全に対する配慮不足などが挙げられます。
企業はこの流れを重視し、自社事業に関わる全ての労働者(正社員だけでなく、契約社員やアルバイト・パート社員等を含む)の人権はもちろんのこと、取引先の労働者、さらには顧客・消費者までの全ての人権を尊重しなければなりません。自社外で起こる人権問題を把握し、それを解決することは容易ではありませんが、自社の社員が顧客・消費者や取引先の社員に対して差別的な対応を行う、また工場建設のために住民に立ち退きを強制するなどの問題が発生しないよう、「自社における人権啓発と教育」を徹底し、それを「連鎖」させる行動が求められています。
人権を尊重する社会の構築には、行政や地域における行動に加え、企業の実践力が不可欠です。企業が持つ「価値」を知り、その価値を応援していくことで、社会の好循環が生まれるはずです。
それぞれの「立場」【1月号掲載】
日本に在留する外国人の数、約341万人(2023〈令和5〉年末現在)。それぞれの目的を果たすため日本で生活していますが、言語、宗教、文化、習慣などの違いから、外国人をめぐる人権問題(アパートへの入居拒否、就労の際の不合理な扱いなど)が注目されています。
2022(令和4)年、内閣府の人権擁護に関する世論調査における"日本に居住している外国人に関し、体験したことや身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことは?"との質問では、1.風習や習慣などの違いが受け入れられない(27.8%)2.就職・職場で不利な扱いを受ける(22.1%)3.差別的な言葉を言われる(19.5%)といった回答が挙げられています。
この調査が実施された同年には、岡山市内の建設会社で働く技能実習生に対する人権侵害行為が大きく報道されました。これは外国人の技能実習生が、職場の同僚などから2年に渡り、暴言や暴行を繰り返し受けた事件で、外国人技能実習機構への通報によって発覚したものです。
技能実習生に限らず、日本で生活する外国人は、言葉が通じないことによるミスや習慣の違いによる誤解や誤認などに対する不安を抱えながら生活しています。
その一方で、これまでに祖国で培ってきた大切な文化や生活習慣などからの転換が容易ではないことを理解してほしいという願望も持ち合わせています。
日本に多くの外国人が生活しているように、多くの日本人が諸外国で同じような不安を抱え過ごしています。国際的な広い視野に立ち、各国の文化や生活習慣を理解し、それを受け入れ尊重していくことが、「共存」の基本姿勢です。
外国人をめぐる人権問題(偏見や差別)をなくしていくことは、社会基盤の強化につながります。それぞれの立場を思いやり、同じ地域で暮らす一員として「助け合う」ことが、言葉や文化の壁を乗り越える有効な手段となるでしょう。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 人権・部落差別解消推進課 啓発推進係(人権啓発センター)
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館1階)
電話番号:0973-22-8017(直通)
ファックス番号:0973-22-8259
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









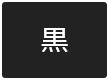
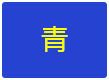
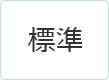
更新日:2026年01月01日