特定外来生物について(植物)
特定外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他の地域から持ち込まれた生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定されている生物のことを言います。
現在、特定外来生物には132種類(平成28年10月1日時点)指定されており、市内においても、植物では「オオキンケイギク」、「アレチウリ」、「ブラジルチドメグサ」、「オオハンゴンソウ」の計4種類が確認されています。
これらの特定外来生物は、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いが規制されており、違反すると懲役や罰金といった罰則があります。
市内の特定外来生物(植物)は以下のとおりです。特定外来生物の拡散防止にご協力ください。
オオキンケイギク

《解説》
北米原産でキク科の多年生草本であり、5~7月にかけてコスモスに似た黄色い花を咲かせます。葉は細長いへら状で、両面に荒い毛が生えています。
とても強靭で繁殖力もとても強く、いったん定着してしまうと、在来の野草の育成場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまいます。
道路の法面や河川敷、庭先など様々な場所で確認できます。
《駆除のポイント》
・根から抜き取る。
・種子の拡散を防ぐため、袋などに入れて枯死させる。
・市指定の袋に入れ、燃えるごみとして処分する。
環境省「オオキンケイギク啓発チラシ」 (PDFファイル: 597.3KB)
アレチウリ

《解説》
北米原産でウリ科の一年生草本で、育成速度がとても速いつる性植物です。
果実には鋭い棘が密生しています。開花期は8~10月で、開花から10日ほどで結実します。冬には枯れてしまいますが、大量の種子を土壌中に残すと翌年も大発生する特徴を持っています。
つるを伸ばして他の植物を覆うように繁茂するため、他の植物に届く光を遮り、成長を妨げるなど、在来植物に悪影響を及ぼすことがあります。
《駆除のポイント》
・種子をつける前に抜き取る。
・できるだけ小さいうちに抜き取る。
・年に数回抜き取る。(土壌中に種子が残っていると再度発芽するため)
・アレチウリが現れなくなるまで数年間続ける。
ブラジルチドメグサ

《解説》
南アメリカ原産のセリ科の多年生草本で、川岸や水源地などに生える植物です。泥に根を張り生活するとともに、水面に浮遊して分布を拡大していきます。茎はばらばらになり易く、ばらばらになった茎の切れ端の節から葉や根を出して生長していきます。
水面に浮遊してマット状に群生するので、光などが奪われて在来の水草類が駆逐されるとともに、水中の溶存酸素の減少により水生生物の生息環境が奪われるおそれがあります。
《駆除のポイント》
・根から抜き取る。
・茎の切れ端の節から生長するため、下流に流さないようにする。
・乾燥させ、燃えるごみとして処分する。
オオハンゴンソウ

《解説》
北アメリカ原産のキク科の多年生草本で、寒冷な土地や湿った環境を好む植物です。開花期は7~10月で、黄色い花を咲かせます。垂れ下がった舌状花が特徴です。
オオキンケイギクには及ばないが、繁殖力旺盛で、一度根付くと根絶が難しい植物です。
また、地下茎から種の発芽を抑制するアレロパシー(多感作用)物質を分泌し、他の植物を発芽させない性質のある植物です。
《駆除のポイント》
・根から抜き取る。
・種子の拡散を防ぐため、袋などに入れて枯死させる。
・市指定の袋に入れ、燃えるごみとして処分する。
外来生物による被害を防止するために、以下のことに気をつけましょう!
外来生物被害防止三原則
1.入れない
~悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない
~飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない
~野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 環境課 水・環境係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8357(直通)
ファックス番号:0973-22-8241









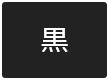
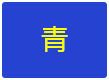
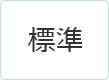
更新日:2021年03月31日