令和7年5月定例記者会見

令和7年4月の定例記者会見の内容、配布資料等は、下記からご覧ください。
動画配信
定例記者会見の動画を日田市公式動画チャンネル『Hita Tube』で配信しています。
5月の定例記者会見動画は、下記リンクをご確認ください。
配布資料
令和7年5月定例記者会見資料 (PDFファイル: 2.7MB)
関連リンク
会見録
【注意】市長、担当課及び記者等の発言内容については、単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、作成しています。
市長あいさつ
おはようございます。本日の案件は5つございます。1番目の「こども総合局(仮称)創設プロジェクトチームの設置」でございますけれども、こども総合局の創設は、選挙時の公約の1つでございました。不登校のこどもへの支援ですとかこどもの貧困対策、障がい児支援、児童虐待防止など、保健福祉・教育の枠を越えて、こどもを真ん中に総合的に支援するための組織の設置について、検討を進めるために、プロジェクトチームを設置いたします。
そのような「こどもまんなか社会」の実現のための組織づくりの検討に着手しようとしている最中に、市立小学校教師の児童に対する暴力行為が起きたことは、本当に痛恨の極みでございます。
被害者への誠意ある対応と再発防止に、教育委員会と協力して、市長としても最大限の努力をして参ります。教育委員会では10年ほど前に、体罰に関して調査、研修を徹底して行い、その後も毎年研修を行っていると聞いておりますけれども、このような事件が起きたということは、結果として徹底できていなかったということでございますので、二度とこのような事件が起きないように、教育委員会とともに、市長としても取り組みます。それが被害に遭われた児童や保護者の最大の願いでもあるというふうに聞いております。安心安全な学びの場としての学校は、日田市の教育の基本でございます。現在、市と教育委員会の協議の場である総合教育会議で教育大綱の見直しを進めておりますけれども、その中でも、このことはしっかり位置付けたいと考えております。
2番目の案件は、本年4月からの文化スポーツ観光部の設置に伴う文化財施策の見直しについての報告でございます。咸宜園については、観光施策との連携によりその魅力と価値を国内外に発信して参ります。小鹿田焼の里については、池ノ鶴では農業が棚田で営まれていること、皿山では、小鹿田焼が作られていること、これが、小鹿田焼の里の景観を価値づけているとの考え方から、石垣や建物というような、物の保存に偏り過ぎていた施策のやり方を見直して、文化財保護と観光・生業・生活の両立を目指そうとするものでございます。以上2件を含めまして、詳細は各担当部局から説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
案件
「こども総合局(仮称)創設プロジェクト・チーム」の設置について(福祉総務課)
○福祉総務課長
福祉総務課長の青木と申します。今年度より、機構改革によって新設となりました課であります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは会見資料の1ページをお願いします。「こども総合局(仮称)創設プロジェクトチームの設置について」であります。後程触れますけども、今後組織の枠を超えた横断的なプロジェクトチームの設置に当たり、事務局長が予定されている立場において、私の方からご説明をいたします。現時点、仮称としていますこども総合局については、先の3月市議会定例会開会日の冒頭に市長から、令和7年度施政執行方針で表明がありました通り、令和8年4月の創設を目指し、組織が果たすべき機能や役割、また、あるべき姿を検証するため、この度庁内に「こども総合局(仮称)創設プロジェクトチーム」を設置することとなりました。目的は、日田市に住むこどもの視点に立ち、こどもたちの健やかで豊かな成長を社会全体で後押しする「こどもまんなか社会」の実現を見据え、こどものライフステージに応じて切れ目のない支援が可能となるよう、こども施策の司令塔役となる組織の創設を目指すものです。
プロジェクトチームの構成員は、総務企画部長をリーダー、福祉保健部長と教育次長をサブリーダーに、また、総務企画部、市民環境部、福祉保健部、教育庁に所属する関係課長で構成いたします。加えまして、この中に、実務面において、分野ごとの検討や協議等を担当するため、総務、福祉・保健、教育の3つの部門でそれぞれ「作業班」を設置いたします。
そこで、市では、5月16日金曜日、午前10時15分から庁議室、この会場ですけども、市長からプロジェクトチームの構成員に対する辞令交付と合わせまして、第1回プロジェクトチーム会議を開催いたします。記者の皆さんには、冒頭の辞令交付式のみ公開とさせていただきまして、別途第1回会議終了後に、取材の時間を、この会場で設けたいと考えておりますので、なにとぞご理解・ご協力の方よろしくお願いいたします。
スケジュールとしましては、年内を目途に、組織の在り方についての結論を踏まえ、組織に関する関係例規等の整理を行った上で、こども総合局の、令和8年4月の創設を目指すこととしております。
続きまして会見資料の2ページから4ページにかけての資料で、補足の説明をさせていただきます。まず資料2ページをお願いいたします。項目2のプロジェクトチームでの主な検討事項としまして、まずは現状で福祉・保健や教育の各分野の施策を実施する上で、既存の各分野の枠組みや体制では対応が困難なケースや、時間を要するといったケースを抽出し、検証していきます。例としまして、こどもの貧困対策、障がい児などの支援、児童虐待防止、様々な要因で不登校や高校を中途退学してしまうこどもへの支援などが現状考えられる分野でございますので、こうしたケースを早期に発見し、適切な支援につなげる観点や、気兼ねなく様々な制度やサービスを利用できるようにする観点等から福祉分野と教育分野の連携の在り方を検討していきます。こうした検討を踏まえ、最終的には、組織の機能や役割の整理、取組を効果的・効率的に推進するための組織機構の整理について検討して参ります。
項目3のプロジェクトチームの構成については、資料4ページの名簿の方をご覧いただきたいと思います。市長から辞令を受ける対象職員は、現時点では表の上段に記載します12名の管理職職員とし、先ほどご説明いたしました3つの作業班の班長としまして、総務部門に総務課長、福祉・保健部門にこども未来課長兼こども家庭相談室長、教育部門に教育総務課長を充てることとしています。また事務局員としまして、表の下段に記載している通り、3つの作業班の主要な部署を担当する主幹総括級の職員をそれぞれ置き、私、福祉総務課長が、その事務局長を兼ねる形で、一体としてプロジェクトチームを構成いたします。前後しますが、資料3ページの方をご覧ください。こうした体系のもとで、項目4のプロジェクトチームでの検討の進め方においては、アドバイザーとして、こどもの分野、また教育分野の専門的な知見をお持ちの大学教授等の学識経験者を選定し、プロジェクトチーム全体の議論に関わっていただき、ご意見やご助言などをいただく予定としております。また、先進自治体を視察し、行政担当者との意見交換を行うほか、こども・若者や、子育て等をなさる当事者などからもお話を伺う機会を設け、意見集約も進めていく予定です。
今後のスケジュールとして、繰り返しになりますが、プロジェクトチームでの検討過程において、まずは福祉と教育で、抱える課題等の実態把握と、諸課題に対する論点の整理、次いで、各論点に対応した支援の在り方の検討を行い、こうしたことを踏まえ、最終的には、日田市が目指すべき組織の在り方の検討などを経て、関係例規等の整備を行った上で、令和8年4月に、仮称でありますが、こども総合局の創設を目指して参ります。
今回のプロジェクトチームでは、組織横断的な取組となり、多くの職員が事務に携わることとなります。福祉分野と教育分野の連携の在り方は、長年課題とされてきたところであり、検討のハードルは高いことが想定されておりますが、関係職員一丸となって知恵を出し合いながら、日田市の「こどもまんなか社会」の実現に向けて取り組んで参ります。
なお、この件に関する問い合わせにつきましては、会見資料の1ページの下段に記載しておりますが、プロジェクトチームに関することは、福祉保健部の福祉総務課まで、個別の事項として、福祉・保健に関することは、同じく福祉保健部のこども未来課まで、教育に関することは、教育庁の教育センターまで、それぞれお願いできればと思っております。長くなりましたが、私からの説明は以上となります。
日本遺産「咸宜園」と「豆田町」の観光連携強化の取組及び国の重要文化的景観「小鹿田焼の里」保存計画の見直しについて(文化財課)
○文化財課長
文化財課、片桐です。座って説明させていただきます。会見資料の5ページをお願いいたします。
日本遺産「咸宜園」と「豆田町」の観光連携強化の取組及び国の重要文化的景観「小鹿田焼の里」保存計画の見直しについて、ご報告させていただきます。
まず、1の取り組みでございます。茨城県水戸市、栃木県足利市、岡山県備前市と本市で構成する教育遺産群世界遺産登録推進協議会の取組であります「日本遺産近世日本の教育遺産群ー学ぶ心・礼節の本源ー」につきましては、昨年7月、観光入込客数の減少等を理由としまして、再審査となった後、同年10月に国の総括評価・継続申請の再審査を受け、その結果、「認定継続」となったところです。再審査の評価結果を受けまして、協議会の組織に各市の観光部局や観光関連団体を加えた新たな部会を設置する予定でございます。
今後の取組につきましては、日本遺産の目的でもあります観光振興、地域活性化の推進に向けて、4市連携のもと、関係機関や各種団体と連携した事業に取り組み、文化観光の推進を図ってまいります。日本遺産の観光誘客の取組につきましては、日本遺産「咸宜園」の魅力を全国、世界に発信し、「咸宜園」と「豆田町」をつなぐ観光誘客に取り組むため、今年度は体験型コンテンツの充実を図り、観光協会や旅行社と連携した着地型旅行商品の造成や、モニターツアーを計画しております。今後、詳細が決定次第お知らせいたします。
続きまして、2の取り組みでございます。池ノ鶴、皿山地区は、平成20年3月に国の重要文化的景観「小鹿田焼の里」として選定されており、「小鹿田焼の里文化的景観保存計画」に基づき運用されています。 住民の暮らしと生業を過剰に規制しないことが景観を守ることに繋がるとの考えの下、今般、災害等で壊れている箇所について「重要な構成要素」から外しました。重要な構成要素は、小鹿田焼の里の景観を構成する上で、重要な要素として位置づけられており、修復したり壊したりするときに規制がかかるものでございます。現在540件特定されております。今回、外した重要な構成要素は、主に池ノ鶴地区の農地、畦道、棚田石積など178件になります。
今後の取組につきましては、重要文化的景観の小鹿田焼の里は、生業や、生活の営みがないと素晴らしい景観は育まれないことから、文化財の保護と観光・生業・生活との両立をめざし、地元の方々と丁寧に引き続き話をしながら規制緩和に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
私からは、以上でございます。
令和7年度日田市合同防災訓練の実施について(防災・危機管理課)
〇防災・危機管理課長
防災・危機管理課長の梶原です。 日田市では、令和元年度から市内小学校の校区を対象として「日田市合同防災訓練」を行っています。本年度は、日隈小学校校区において、日隈小学校をメイン会場として行います。 日時は、令和7年6月1日 日曜日 午前8時から午後1時です。
訓練には、自衛隊・警察・消防・消防団などの防災関係機関、日本赤十字社大分県支部をはじめとする各種団体及び日隈校区の住民が参加します。また、日隈校区内の福祉施設・商業施設にも訓練参加の調整を行っているところです。訓練の大きなねらいは、出水期前に関係機関・団体・行政が顔見知りになり、例年 豪雨が予想される梅雨末期を想定した災害対応において円滑に連携できるような体制の確認及びその強化を図ることとしています。
訓練内容につきましては、市役所庁議室において収集した情報に基づき、避難所を開設し、関係の機関と団体が連携・協力をして人命救助訓練などを行います。また、先端技術を活用した訓練実施も計画しています。具体的にはドローンを使用して、今年度日田市で導入を予定しているスターリンクを避難所へ輸送します。このスターリンクを使用して通信手段を確保し、大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの遠隔操作ロボット・アバターを活用した遠隔健康相談を計画しています。 災害により孤立集落が発生した際の、通信手段の確保の検証を踏まえた訓練となります。
日田市として市民の皆様の生命・財産をお守りするため、防災訓練を通じ防災思想の啓発に取り組んでいます。災害は、いつどこで発生するかわかりません。ぜひ、防災訓練を見学していただいて防災への関心を深めていただきたいと考えています。私からは以上でございます。
第78回日田川開き観光祭の開催について(観光課)
〇観光課長
皆様お疲れ様です。観光課でございます。私の方から案件4番目の「第78回日田川開き観光祭」の開催についてお知らせします。資料の方は9ページと皆様のお手元にございますこちらのパンフレットと、花火プログラムの方に記載のある内容でご説明をいたします。
水郷日田に初夏の訪れを告げる最大のまつり、「第78回日田川開き観光祭」の開催についてご説明します。「第78回 日田川開き観光祭」は、5月24日(土曜日)・25日(日曜日)の両日、三隈川周辺、日田駅南広場、中央公園及びにパトリア日田などを会場に開催します。
次に、内容についてです。5月24日(土曜日)、午前10時から祭りの最初の行事として「水の事故や災害が起きないように祈りをささげる神事」となります水神祭が開催されます。
川に触れ、親しむイベントとして、京町児童公園下の三隈川周辺を会場に、24日(土曜日)午前11時から「ハンギリ源平合戦」、三隈川周辺(庄手側)を会場に25日(日曜日)午前9時から「YEG CUP ダンボールボートレース」を開催します。また、亀山公園を会場に午前10時から「SPLASH カラーバトル・謎解きウォークラリー」を開催します。
次に、25日(日曜日)、午前11時20分頃から、中央公園付近の寿通りから日田駅前までの区間で、水郷日田どんたくカーニバルが開催されます。このパレードには、最初にパレード隊として、ひた魅力発信隊や木レンジャー(もくれんじゃー)、市内認定こども園が参加を予定しています。
午前11時40分頃から、市内20団体が出演するパフォーマンス部門が行われます。今回から新たに表彰内容に「特別賞」を追加しています。
続きまして、日田では、全国的にも珍しい小学生の鼓笛パレードの取組をはじめ、日隈小学校や高校吹奏楽部でも全国大会やイベント等で盛んに活動されています。今回、川開き観光祭を通して芸術文化を体験できるイベントとして、マーチング・イベントを開催し、多くの方にマーチングの魅力を感じていただき、日田の魅力を知っていただきます。また、マーチング・イベントを盛り上げるため、全国で活動されている吹奏楽部を招聘し、「マーチングが盛んなマチ」として発信いたします。
先ず、オープニング・イベントとして、24日(土曜日)午前10時から、咸宜小学校を出発し、日田駅南から竹田公園までの区間で、市内小学校12校、中学校1校、高等学校3校の総勢約1,200名が参加する「音楽大パレード」が開催されます。 また、25日(日曜日)午前10時からは、日田玖珠地域産業振興センター前を出発し、本町交差点前までの区間で、市内小学校1校、高校3校、大分商業高等学校吹奏楽部、神村学園中等部・高等部吹奏楽部の総勢 約300名が参加する「マーチング・パレード」が開催されます。同日、午後2時から、パトリア日田・大ホールを会場に「マーチング・フェスタ」を開催します。
この他、24日・25日の両日に開催されるイベントとしまして、三隈川では、2日間で約1万発を打ち上げる「大花火大会」を午後7時40分頃から午後9時頃の時間で開催します。
中央公園では、「奥日田ファンゾーン」として、フォレストアドベンチャーモバイルや、鯛生金山の宝石探し、トライウッドの積木やパズルなどがあります。
駅前南広場では、今回、初めてYES,BECKEN!!チームとコラボしたイベントを開催します。これまでの出店者と合わせて、農業や林業に触れる機会やイベントを創出します。
つづきまして、日田市では「日田市ポイ捨て条例」が制定されていることから、ボランティアの方を中心に「ひろえば街が好きになる運動」を中央公園横で実施しています。
イベント会場付近の駐車場は大変込み合います。イベント会場と駐車場を巡回する「シャトルバス」を運行していますので、ご利用ください。また、花火大会終了後には、臨時列車、臨時高速バスを運行します。
花火大会時の両日、車椅子用の観覧スペースにつきましては、三隈大橋の下に準備するとともに、授乳室・おむつ交換所を隈集会所と合わせて今年度から京町集会所にも設置します。
その他、詳細につきましては、お手元のパンフレットをご確認ください。私からは、以上でございます。
令和7年5月行事予定(総務課)
5番の令和7年5月の行事予定表は、資料最後の予定表をご確認ください。
質疑応答
〇記者
文化的景観の見直しのことについてお伺いします。先ほど説明の中で、教育遺産群の関連のことについて再審査から認定継続というふうなプロセス説明があったんですけれどもここの部分をちょっともう少し詳しく教えていただきたいというのが1点と、あと、このときに指摘されたことというのが、観光客が少ないというふうなことが主なポイントというふうなこと認識でいいのか。また、指摘された方としては、また違うところに問題意識があるだとかいろいろ日田市側の考えもあるかと思いますので、そこも併せて、今後観光協会等に委託して、着地型旅行商品の造成というふうなことがあるんですけれども、具体的な内容がもう少しわかれば、そこも含めて教えていただければと思います。
〇世界遺産推進室長
まず日本遺産の再審査につきましては、現在の仕組みとしては3年間の取組み、4年目に審査をするという流れがありまして、第1回の申請については日田市を含む4市の協議会は、令和3年度に、審査を受けました。その時には再審査にはならなかったんですけども、今回令和3年度から5年度までの3ヵ年間の取り組みについて、6年度の審査においては、再審査という結果になったものでございます。その内容としましては、指摘事項として国が大きく、指摘としていただいてるのは、認定時は平成27年度になるんですけども、認定時の観光客の4市の入込客数の総数が、令和5年度までの数字を見た限りですね、実際に減っているということもありまして、令和5年度の段階においても、認定時から減っていたという事実を受けてですね、これが最も大きな指摘事項でありました。次には現在行政主導でやってる取り組みが、私どもの取組として多かったんですけども、民間の事業者を活用した取組をもっと活性化することということも大きな指摘事項とされています。そのようなことから、昨年度の再審査を受けた後に、まず咸宜園世界遺産推進室においては、新たな取組としまして、関係者の協力を得て、昨年の天領まつりから新しく咸宜園マルシェということで、キッチンカーを導入いたしました。それと、12月にはパトリアの協力を得まして、梅川壱ノ介さんの日本舞踊の取組、また今年の3月には、咸宜園十三祝いの会と言って市内の小学6年生を対象とした新たな取組をするなどして、活性化しているということでございますが、今日のリリースの資料の中にもありましたように、今年度は文化スポーツ観光部となったことからですね、観光課の方でも一部、日本遺産のツアーを企画しておりますので、観光課長からもお話をいただきます。
〇観光課長
観光課の取り組みについてご説明します。現在、観光で豆田町に訪れるルートとしては、高速バスを降りて丸山側から入ってくるルートが多くなっております。またもう1点は、豆田町に訪れる観光客については、インバウンドが急増しておりまして、インバウンドのニーズについては、やはり日本文化の体験が人気となっております。このような中で、世界遺産推進室長からも説明がありましたが、昨年から天領まつりでマルシェを合同で開催したり、ひなまつりの協賛で十三祝いの会を開催し、こちらの方では、和服体験やお茶会をやっております。現在、観光協会と詳細を詰めておりますが、日本の文化を咸宜園で体験してもらうようなコンテンツを充実させて、まずは咸宜園に訪れた方が今度は豆田町に行ってもらうような着地型の商品を一緒に作っていこうという考えでございますので、また詳細が決まりましたら情報を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
〇記者
ありがとうございます。着地型の観光商品、概ね今後のスケジュールとして観光シーズンいろいろあります、ポイントにしたい時期だとかあると思うんですけれども、この時期までにというふうな目途はありますでしょうか。
〇観光課長
目標としては、秋までには造成したいと考えています。秋が一番日本文化を感じる季節的にも良いかなというふうに考えておりますので、一応目標としては、秋を予定しております。
〇記者
文化的景観の部分の特に池ノ鶴の方のことだと思うんですけれども、この4月22日付での見直しというのは、国の計画を見直したそれとも日田市の計画を見直したどう表現がいいんでしょうか。
〇文化財課長
日田市の計画です。
〇記者
わかりました。検討会というか会議か何か開いて、それで最終的に見直しということなんですか。
〇文化財課長
この件に関しましては、まず所有者さんがいらっしゃいますので所有者さんと話をして、また、景観委員会というものがありますのでそこで、先生方も文化庁、県、市と、地元代表の方の入った中でお話をして、その上で再度、所有者さんの承認を得まして、保存計画の変更という形で、文化庁の方に県を通じて、報告を上げております。
〇記者
「4月22日で変更した」という言い切り方で良いんでしょうか。
〇文化財課長
そうですね。はい。うちの方はそれで、いっております。
〇記者
今後のことなんですけれども、例えば復旧だとかですね、3軒しかないだとかっていうふうになって実質的にはどうなのかっていうともっと少ない現状もあると思うんですけれども、これが今後どういうふうに生かされていくというふうに考えてらっしゃいますか。
〇文化財課長
棚田の復旧に関しまして話をすれば、所有者さんの意向もあると思いますが、農業を続けたいという意向であれば、農業振興課の方と話をして何ができるのか、どうやっていくのかというところの用途を考えやすくなったというところがありますので、具体的に動きがしやすくなったのではないかというふうに思っております。
〇記者
もうちょっと具体的に聞くと、現状復旧以外の道も選択肢として用意できるというふうな認識でよろしいですか。
〇文化財課長
そうですね。はい。
〇記者
砂防ダムの件とかっていうのもこれに関わってきますでしょうか今後大分県が計画されている。
〇文化財課長
はい、もう今建設しておりますので。そこを作る時には文化庁に話をした上でしておりますので。
〇記者
この178件というのがどこなのかっていうのは何かリストのようなものがもしあれば、何か見せてもらえればいいかなと。
〇文化財課長
そうですね。ちょっとわかりづらいという点があって、非常に皆さん書きづらいかなというところがありまして。例えばですね、棚田1つに4つとか5つとか関連してるんですよ。農地の面、石積、畦、耕作道というような形でですね、1つの田んぼで、1件ではなくて、それに構成要素という表現があるんですけど重要な構成要素となるんですが、そこが4つ一緒になって、1つの田んぼみたいな感じになるので、非常に件数的には多いというふうに考えられるかなあと思うんですが、うちの計画はそういうふうな特定になっておりますので、今回540あるうちの178という表現になっております。
〇記者
最後の方のことなんですけれども、誤指導の問題というのが過去にありました。自宅の改修についてももうちょっと柔軟にして欲しいというふうなご意見が地元の方からありまして今回の見直しでそこも反映できるような形になっているんでしょうか。
〇文化財課長
今回、毀損届といって災害に遭ったときに、壊れてますという届け出を出したものが中心になっておりますので、これからですね、第2弾として、全体的にこの運用について見直していきたいというふうに思っております。まず何をしたいのかというと、やはり先ほど言われたように、規制がかかっておりますので、文化的景観の保護の措置というのはですね、景観法の方の規制がかかっております。そこを、まずは規制緩和をしていきたいというふうに考えております。
〇記者
小鹿田焼の件で、ちょっと引き続きよろしいですかね。4月22日付で市が変更したってことですね。その手続きなんですけど、今課長おっしゃったように変更やってその県を通じて文化庁に報告をしたと。この報告もこの22日付けをもってってことなんでしょうか。
〇文化財課長
そうですね、日付は22日付で大分県の方に出しております。その後、大分県から質問がありましたので、また大分県が文化庁にいつにしたのかっていうのはちょっとまだ確認取れてませんが、うちの方は22日付で、県の方に出しております。
〇記者
市としては22で変更ということになりますが、それで最終的にその選定したのは文化庁長官だと思うんですよね。文化庁側からのリアクションっていうのは現時点でどうなんでしょう。
〇文化財課長
今、何もないです。その前にですね、文化庁の方に出向きまして、こういうふうに考えたいというところの協議は行って参りましたので、ご理解いただいた上で、今回、計画の変更を行ったというふうな形になります。
〇記者
事前の地ならしを当然やってたということになりますよね。
〇文化財課長
現状をご理解いただいたのかなというふうに思っております。
〇記者
オフィシャルの形で報告を受けて、文化庁が何がしかの言葉として何かを承認するとかね、そういうのっていうのは、行政手続き上あるんでしょうか。
〇文化財課長
ないんじゃないかなと思っております。
〇記者
計画は日田市の計画というところではありますので、あと、今、これもまたちょっと確認っていうか、さっきおっしゃったと思うんですけども、今回は災害対応がメインでやっていらっしゃって、第2弾としては見直しを考えていると。これを第2弾ていうのは、議会で過去に何度も取り上げられた10数年どうだこうだって話に該当するわけですね。それで、景観っていうのは基本的に規制かかってて、緩和をするっていう流れで今回動かれてるんですけどもその景観を保持する以上規制がかるのは、僕は当たり前だと思うんですよね。あともう1つは、計画の中で、これ、今回の機構改革とも絡む話でしょうけども、市長もさっきおっしゃった保存と活用の両立もっていうのが1つ大きなポイントになると思うんですけども、現時点、その活用の部分、観光資源としての活用の部分っていうのがなかなかやっぱり少なくとも、特に池ノ鶴の場合はですね、見えてこないんですけども、その辺りを第2弾で見直しにってどのように取り組むつもりなのかっていうのを1つ教えてください。
〇文化財課長
非常に厳しい現実かなというふうには思っています。なので、所有者の方も含めてですね、どういう手法がいいのかというのは、これから皆さんの知恵を借りながら、検討していきたいと思ってます。
やはり文化財はですね、人がいないとほぼできない。やはり専門家の方とか、すごい知見のある方だけではですね、やはり今後守っていけないんじゃないかというところで、今年度地域計画というのをうちの方も策定しました。やはりみんなで総がかりで守っていくというところがないと、後世に続いていけないというところもありますので、やはりその辺をどういうふうに皆さんに伝えていくかということになるとやはり観光目線とか、皆さんに知ってもらうというところの連携を含めながら、価値づけていく、価値を高めていくというようなものになっていくんじゃないかというふうに考えております。
〇記者
最初の議題、こども総合局のところで1つだけ、先進自治体の視察も今後の予定で入ってるんですが具体的にどこか教えてもらえませんか。
〇福祉総務課長
今後、先進自治体の視察を予定はしているということでご説明したところですけども、全国的に見ても、まだ調査不足のところもありますが、そう多く、日田市が考えているような組織を設置をしてるっていうところが、そんなに多くはないようにちょっと記憶してます。これから調査を進めて参りますけども、例えば1つの例でいきますと、新潟県の三条市ですとか、岐阜県の岐阜市、こういったところは、そういった近しい組織があるというふうなところで情報は掴んでおりますので、それ以外にもちょっと調査、研究を進めていきたいというふうに考えております。そういった調査研究の中で、先進自治体についてはまた選考していきたいというふうに考えております。
〇記者
こども総合局のことで教えてください。今回の対象の年代なんですけれども、概ね何歳から何歳までのお子さん、もしくはそのご家庭というふうなことを想定されてらっしゃるのか。年代年齢、18歳以上になってくるとなかなか福祉サイドでサービスが、思うようにいかなかったりっていうふうな課題もあるかと思うんですけれども、高校世代だったり、大学を中退してとかっていうふうな話も、おそらく課題として上がってくるのかなと思いますがそうなってきたときに、何歳ぐらいのお子さんまでを包括して見ていくのかっていうふうなことは1つ大きな課題なのかなと思うんですけれども。
〇福祉総務課長
現時点どうっていうことではまだ決定はしてないんですけども、一方こども基本法という法律がありまして、そちらの方でいうこどもの定義の中には、具体的年齢規定が特段設けられていないものでありますけど、心と身体の発達の過程にある人、というふうに定義づけされております。一方で年齢によって必要なサポートが途切れないようにするというような観点も当然ありますし、今後、こども政策を総合的に取り組んでいく、組織体制を整備している自治体、先進自治体、そういった事例も、ちょっと今後参考にしながら検討していきたいというふうに考えております。
〇記者
有識者のことがあったかと思うんですけれども現段階で決まっていましたら教えてください。
〇福祉総務課長
現在まだ選定の途中であります。先ほどご案内しましたように、5月16日に第1回プロジェクトチームの会議を設けます。できれば、この会議の方に有識者の方も参画いただけるようにしたいと考えておりますので、早急に選考を進めて参りたいと考えております。
〇記者
防災訓練のことで1点教えてください。スターリンクの輸送なんですけれども、どこからどこに行くのか、何時ごろ。ここちょっと取材したいなと思ってまして。
〇防災危機管理課長
スターリンクの輸送につきましては、資料の7ページの下に記載のとおり、中ノ島の方からメイン会場であります日隈小学校のグラウンドの方に運ぶ計画をしております。今、ドローンの使用について、協議、計画を詰めている段階でございます。
〇記者
なので日隈小学校の方には、避難所として開設されていてここに住民の方とか、ボランティアの方とかもいらっしゃるような状況で、実際にそのスターリンクを使って、市役所とやりとりするとかっていう動きになるんでしょうか。
〇防災・危機管理課長
日隈小学校会場に送りましたスターリンクを使用した通信試験等を予定しております。
〇記者
はい、わかりました。ありがとうございます。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市総務企画部 企画課 広報・広聴係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8627(直通)
ファックス番号:0973-22-8324
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









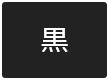
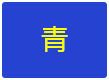
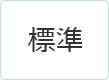
更新日:2025年05月14日