土地への課税
評価の仕組みと価格(評価額)
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって、地目別に定められた評価方法で評価します。
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
宅地の評価については、平成6年度評価替えから、地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割をめどとして評定しています。
地目と地積
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、山林、原野、雑種地等があり、固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって課税することとなります。
具体的な地目については、次のようになります。
- 宅地
建物の敷地及びその維持、効用を果たすために必要な土地 - 田
農耕地で用水を利用して耕作する土地 - 畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
地積は、原則として登記簿に登記されている地積を使用します。
宅地の評価方法
宅地の評価方法には、市街地宅地評価法(市街地の場合)と、その他の宅地評価法(市街地以外の場合)があります。
具体的な評価方法については、次のとおりです。
- 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。
- 区分された地区、地域において標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
- 地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として主要な路線の路線価を付設します。(市街地宅地評価法)
- 街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量し、その他の街路の路線価を比準、付設します。(市街地宅地評価法)
- 地区、地域内の各筆の評価を行います。
住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地には、専用住宅の敷地と併用住宅の敷地があり、専用住宅の敷地は敷地の面積(家屋の床面積の10倍まで)とし、併用住宅の敷地は敷地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地を対象にしています。
また、住宅用地には、課税標準額について次の特例措置があります。
1.小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置(都市計画税は3分の1)があります。
2.一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地になります。一般住宅用地は、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置(都市計画税は3分の2)があります。
土地の課税標準額の算定
1.課税標準額
課税標準額とは、実際に税率を掛けて税金の額を算定するための価格のことです。
土地の課税標準額は、平成6年度に評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割をめどとする評価替えが行われたことに伴う負担調整措置等により、実際の評価額より低い価格で課税されている場合があります。
2.負担水準
土地によっては、実際の評価額に対する課税標準額の割合にばらつきがあります。土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す割合のことを「負担水準」といいます。
- 負担水準=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地の特例率)
3.負担調整措置
全体の負担水準をある程度の割合に均衡化させるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる措置が導入されています。
この措置を、負担調整措置といいます。
【負担調整措置の具体例】
具体的な例として、事務所や商店等の非住宅用地(商業地等)の場合で計算してみます。
4.税額が下がる場合(負担水準が0.7を超える土地の場合)
- 前年度課税標準額 75万円
- 今年度の評価額 100万円
- 負担水準 75万円÷100万円=75%
負担水準が70%を超えるため、70%まで引き下げられます。
したがって、今年度評価額は100万円ですが、課税標準額は100万円×70%=70万円となり、税額は70万円×1.4%=9,800円となります。(前年度の税額75万円×1.4%=10,500円から9,800円に引下げ)
5.税額が据置きとなる場合(負担水準が0.6以上0.7以下の土地)
- 前年度課税標準額 65万円
- 今年度の評価額 100万円
- 負担水準 65万円÷100万円=65%
負担水準が60%以上70%以下のため、課税標準額は据置きとなり、税額は前年度と同じになります。税額は65万円×1.4%=9,100円となります。(前年度税額65万円×1.4%=9,100円と同額)
6.税額がなだらかに上昇する場合(負担水準が0.6未満の土地)
- 前年度課税標準額 50万円
- 今年度の評価額 100万円
- 負担水準 50万円÷100万円=50%
負担水準が50%と低いため、税額を上昇させることとなりますが、一度に税額を上昇させると納税者の負担が重くなるため、なだらかに上昇する調整措置(負担調整措置)を行います。
今年度課税標準額は、前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を加えたものとなります。ただし、当該価格が評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%相当額とし、20%を下回る場合には、20%相当額とします。
今年度課税標準額=前年度課税標準額+今年度評価額の5%
したがって、上記の例の場合、負担水準は50%となりますので、今年度課税標準額は前年度課税標準額50万円に今年度評価額の5%を加え、50万円+100万円×0.05=55万円 となり、税額は55万円×1.4%=7,700円となります。(前年度税額50万円×1.4%=7,000円から7,700円に上昇)
なお、住宅用地についても同様な税額の調整措置がとられています。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









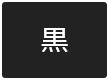
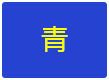
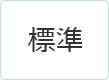
更新日:2021年03月31日