家庭での食育
日田市では「日田市食育推進計画」を策定し、食育を推進しています。
このページでは、学校給食に関連して、小学生・中学生のいるご家庭での食育に役立つ情報を紹介します。
目次
共食
家族や友人と共に食事をとることを「共食」といいます。
食事は単に栄養をとるだけでなく、コミュニケーションを図るためにも重要です。
各家庭でもお子さんと一緒に食事をとりながら、学校での出来事を聞いてみるなど、コミュニケーションの時間を大切にしましょう。
1日3食、規則正しい食事
1日を活動的に過ごすためには1日3食、規則正しい食事が重要です。
特に朝食は1日の始まりの大切なエネルギー源です。
朝食を抜いてしまうと、脳の働きに必要なブドウ糖が足りなくなって、ボンヤリしてしまい、勉強に集中できなくなってしまいます。
大分県のホームページでは、朝ごはんのレシピ集を公開しています。ぜひご覧ください。
手洗い
石けん等を使ってきれいに手を洗うようにしましょう。
手は、普段の生活の中で色々なものにふれます。そのため、気づかないうちに細菌やウイルスがついていることがあり、その菌やウイルスが原因となって食中毒が発生することがあります。食中毒の予防のためにも手洗いは重要です。
また、手洗いは、食中毒予防以外にも、様々な感染症の予防にも有効ですので、手洗いの習慣を身につけていきましょう。
手洗いのポイント
手を洗うときには、洗い方も大切です。洗い方に気を付けることで、洗った後に残るウイルス等の数に大きな差が出ます。
・水だけで洗わず、石けん等を使用する。
・時間をかけてきちんと洗う。
厚生労働省が、衛生的な手洗いの手順をまとめたチラシを配布していますので、そちらもご覧ください。
【厚生労働省チラシ】できていますか?衛生的な手洗い (PDFファイル: 1.2MB)
石けん等は泡立てましょう
石けん等は泡立てて使用することによって、次のような効果があると言われています。
- 手のしわの中など細部までいきわたる。
- 泡が汚れを包み込んで浮かび上がらせることで、少ない摩擦で洗える。
食中毒の予防
食中毒は、家庭の食事でも発生します。
食中毒の発生を防ぐために、下記の点に注意しましょう。
また、厚生労働省が作成した、ポイントをまとめたチラシもありますので、あわせてご覧ください。
【厚生労働省チラシ】家庭でできる食中毒予防の6つのポイント (PDFファイル: 747.3KB)
1.食品の購入
- 表示されている消費期限等を確認してから購入しましょう。
- 購入した食品は、肉汁や魚等の水分が漏れないように、ビニール袋などを使って分けて包んでから、持って帰りましょう。保冷剤や氷等があると安心です。
- 要冷蔵や要冷凍など、温度管理の必要な生鮮食品などを購入するときは、なるべく買い物の最後にして、購入したら早めに持って帰るようにしましょう。
2.食品の保存
- 冷蔵や冷凍の必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れて保管しましょう。
- 肉や魚等はビニール袋や容器に入れて、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁等がかからないようにしましょう。
- 冷蔵庫や冷凍庫に入れていたからといって、食中毒の原因となる細菌等がいなくなるわけではありません。細菌等が発生する前に、食品は早めに食べてしまいましょう。
3.下準備
- タオルやふきんは清潔なものを使いましょう。
- 生の肉、魚、卵を取り扱った後など、こまめに手を洗いましょう。
- 生の肉や魚の調理に使った包丁やまな板を、生野菜などの調理にそのまま使うのはやめましょう。別の包丁やまな板を使うか、洗ってから使いましょう。
- 料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。やっぱり使わなくなった場合など、冷凍や解凍を繰り返すと食中毒の原因となる菌が増殖する場合があります。
4.調理
- 調理中も、こまめに手を洗いましょう。
- 加熱して調理する食品は、十分に加熱しましょう。加熱を十分に行うことで、食中毒菌がいたとしても殺菌できる場合があります。
- 急な用事などで調理を途中で中断する場合は、食品をそのまま放置せずに冷蔵庫に入れておきましょう。調理を再開するときは、十分に加熱しましょう。
- 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付けましょう。熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
5.食事
- 食事の前にも手を洗いましょう。
- 清潔な手で、清潔な器具を使って、清潔な食器に盛りつけましょう。
- 食品は、調理前も調理後も、室温で長く放置するのはやめましょう。
6.残った食品
- 残った食品を扱う前にも、きちんと手を洗いましょう。
- 残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。
- 残った食品は早く冷えるように、小分けして保存しましょう。
- 冷蔵庫などで保管していても、時間が経って、変な臭いがするなど、少しでも怪しいと感じたら、思い切って捨てましょう。
発症するまでの時間
食中毒の症状(腹痛、下痢、おう吐など)が現れるまでの時間は、原因となる食中毒菌等により異なります。
食品を食べた直後に症状が現れることがある一方で、1週間以上経ってから症状が現れることもありますし、個人差や体調によっても異なると言われています。
もしも家庭で食中毒が発生してしまったら
家庭で食中毒が発生したときは、症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず重症になったり、死亡する例があります。
最初は軽い症状でも急激に悪化する場合もありますので、食中毒が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
HACCP(ハサップ)を行ってみましょう
HACCP(ハサップ)という言葉を目にすることがあると思います。
HACCP(危害分析重要管理点)とは、NASA(アメリカ航空宇宙局)が、宇宙飛行士たちの食事の安全性を確保するために考えた方法で、食品の安全を確保するための国際的な衛生管理手法となっています。
危害分析(Hazard Analysis)と重要管理点(Critical Control Points)の頭文字をとってHACCP(ハサップ)といいます。
家庭の調理では、食品と調理過程のどこで食中毒菌による汚染、増殖が起こるか、それを防ぐにはどういう手段があるかを考えることが「危害分析」(Hazard Analysis)にあたります。
また、調理の際に、特に注意を払うべきポイント(上記の6つのポイント)は「重要管理点」(Critical Control Points)にあたります。
家庭でも食中毒が発生する要因を考え、食中毒予防のための対策をしてみましょう。
食品ロス
「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。
日本では、令和4年度の推計で年間472万tの食品ロスが出ていると言われています。
国民1人当たりで計算すると、1年間で約38kgとなり、1日あたりだと約103gになります。これはおにぎり約1個分のご飯の量に近い量を捨てていることになります。
食品ロスを減らすためには
一人ひとりの行動が大切です。
例えば…
- 給食や食事を残さずに食べる
- 食品を買うときに、すぐに使う予定のものは、消費期限等の近いものから買う
- 必要な分だけ買う
などのような、身近なことから始めてみましょう。
食物アレルギー
「食物アレルギー」とは、食物を食べたり触ったりした際に、じん麻疹・湿疹・下痢・咳などのアレルギー症状が起こることをいいます。
また、「食物アレルギー」以外にも、体質的に特定の食品を分解する酵素が不足し、食べ物を消化できない「食物不耐症」という病気もあります。例としては、牛乳のような乳糖を含む食物を食べると、乳糖を分解できず、牛乳アレルギーのように下痢の症状が出る「乳糖不耐症」があります。
食物アレルギーに関する用語
学校給食の中で使われる食物アレルギーに関する用語を紹介します。
アレルゲン
アレルギーの原因となる抗原のことをいいます。
特定原材料
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものとして、表示が義務化されたものです。
特定原材料に準ずるもの
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特定原材料に比べると症例数等が少ないものとして、可能な限り表示することが推奨されたものです。
コンタミネーション
食品を製造する際に、アレルギー物質を含む原材料は使用しないが、製造工程や原材料の漁獲工程などで意図せずアレルギー物質が混入してしまうことです。
アナフィラキシー
アレルゲンなどの侵入により、複数の臓器(皮膚 ・ 呼吸器 ・ 消化器 ・ 循環器 ・ 神経など)にわたって全身にアレルギー症状が現れて生命に危機を与え得る過敏反応と定義されています。
アナフィラキシー反応のうち、血圧低下や意識障害を伴う場合をアナフィラキシーショックといい、一刻も早く医療機関で治療しないと死亡することがあります。
食物アレルギーの症状
食物アレルギーでは様々な症状が出ますが、大きく分けると下記のような症状があります。なお、摂取するアレルゲン量や年齢によっても症状の現れ方が異なりますし、重症化するとアナフィラキシーショックが起きることもあります。
皮膚症状
じんましん、皮膚の腫れ・かゆみ・赤み、湿疹 など
粘膜症状
目の赤み、かゆみ、涙、鼻汁、鼻づまり、くしゃみ、口・唇の違和感 など
呼吸器症状
のどの違和感、かゆみ、飲み込みづらさ、咳、息苦しさ、呼吸困難、チアノーゼ(皮膚が皮膚が青っぽく変色) など
消化器症状
気持ち悪さ、吐き気、おう吐、腹痛、下痢、血便 など
その他の症状
頭痛、意識を失う など
食物アレルギーの発症時期
食物アレルギーは子どもから大人まで年齢に関係なく発症します。
乳幼児期には卵・牛乳・小麦・大豆のアレルギーが多くみられますが、成長とともに自然に治る場合や、病院で適切な診断を受けて治療する場合もある一方で、大人になってから発症することもあるので注意が必要です。
アレルギーかなと気になった場合は、専門の医療機関に相談してみましょう。
家庭での指導
食物アレルギーがあるお子さんには、アレルギーについて話をしましょう。(給食の食べ方・食事制限が必要なことなど)
- 命に関わるアナフィラキシーを起こす場合は、誤って食べてはいけない食品を教えましょう。
- 主治医からの指示内容を、子どもに分かりやすく説明しましょう。
- 食物アレルギーのために食べられない献立がある場合は、必ず一緒に献立表で確認して、何が食べられないかを伝えましょう。
- 学校に飲み薬や塗り薬などの常備薬を持参する場合は、その管理と使用について十分に説明し、確認しましょう。
- 学校で具合が悪くなったときは、すぐに自分で学級担任や周りにいる教職員、児童・生徒に申し出るように、と伝えましょう。
- 同じ食品でも体調によってはアレルギー反応がでる場合があるので、日頃から規則正しい生活を心がけるよう説明しておきましょう。
アレルギーへの理解
食物アレルギーは、好き嫌いとは違います。
食物アレルギーがある場合は、食べたとき以外にも、触るだけで症状が出ることもあります。また、命にかかわる危険な状態になることもあります。
「食べない」のではなく「食べられない」ことをみんなが理解することが大切です。
食べるときの姿勢
背筋を伸ばし、姿勢をよくして食事をすると、お腹が圧迫されないので、消化がよくなるという効果があります。
良い姿勢になるためには、以下のポイントに気をつけてみましょう。
郷土料理
日田市の郷土料理には、
・ハレの日のおもてなし料理として作られてきた「がめ煮」
・昔ながらの素朴なおやつ「へこやき」
・お茶うけや、おせち料理の一品として出される「ゆず皮煮」
・夏場のご馳走としてお盆に作られるようになった「たらおさ」
など、色々な料理があります。
日田市のcookpad(下記のリンク)では、郷土料理のレシピを紹介しています。また、親子で作れる簡単おやつレシピや、管理栄養士おすすめの健康レシピなども紹介していますので、ぜひご覧ください。
地産地消
「地産地消(地域生産地域消費)」とは、地域で生産された農林水産物(食用に限る)をその地域内で消費することです。
お店で日田市産や大分県産の食材を買って食べることも「地産地消」になります。
地産地消のいいところ
- とれたて新鮮なものが食べられる。
- 身近な地域でつくっているので、生産の状況が分かり、また生産者のこだわりなどを知る機会になる。
- 遠くへ運ぶ必要がないので、輸送にかかるエネルギーが抑えられ、環境にやさしい。
- 生産者にとっても、身近な人が食べてくれることで、感想やニーズを直接聞くことができる。
日田市の農産物
下のリンク先から、日田市の農産物を紹介したパンフレットがご覧になれます。
日田産の食材を使うときの参考にされてください。
おおいた食育ウィーク
大分県では、大分県食育推進条例を制定し、その中で11月19日を「おおいた食(ごはん)の日」、おおいた食(ごはん)の日を含む一週間を「おおいた食育ウィーク」としています。
学校給食でも、その週は大分県産の食材をたくさん使った献立になっています。
ご家庭でもぜひ「おおいた食育ウィーク」に大分県産の食材を使った料理を食べてみてください。
給食に使う食材の納入業者募集
県全体の取り組み
上で紹介しました「おおいた食育ウィーク」以外にも、大分県では学校給食で以下のような取り組みを行っています。
うま塩給食の日
「うま塩給食」とは、「うまみ」のある食材を「上手く」活用し、塩分控えめでもおいしい給食のことです。
大分県のホームページでは「うま塩レシピ」を公開しています。家庭でもぜひつくってみてください。
【大分県ホームページ】旨い!上手い!美味い『うま塩(減塩)レシピ』
野菜たっぷり給食の日
「野菜たっぷり給食」とは1食あたり150g以上の野菜を使用した給食のことです。
これは、大分県の立ち上げた「まず野菜、もっと野菜」プロジェクトの一環です。
大分県では、過去の調査で男女ともに野菜の摂取量が少ないことが判明したことから、最初に野菜を食べること(まず野菜)、今より70g多く野菜を食べること(もっと野菜)の推進に取り組んでいます。
大分県の「まず野菜、もっと野菜」プロジェクトのページでは、レシピも公開していますので、ぜひご覧ください。
【大分県ホームページ】「まず野菜、もっと野菜」プロジェクトについて
学校給食地産地消夏野菜カレーの日
食育動画
大分県生活環境部の食品・生活衛生課では、大分県内で生産された農林水産物について学べる食育動画や、県産食材を使ったレシピ動画を公開していますので、ぜひご覧ください。
旬の食材
「旬(しゅん)」とは、野菜や果物がたくさんとれる時期のことです。旬の食材は、おいしくて、栄養も多いです。
下に紹介している以外にも旬の食材はあります。色々な食材の旬を調べてみましょう。(日田市でとれる農産物の旬の時期については、上で紹介している「日田市農産物パンフレット」にも載っています)
なお、地域や品種によって旬が異なることがありますし、しいたけのように旬の時期が複数ある食材もあります。
春ごろ
春キャベツ、新たまねぎ、新じゃが、たけのこ、いちご、あさり、鰹(かつお)、鯛(たい)
夏ごろ
なす、きゅうり、とうもろこし、ゴーヤー、オクラ、桃、鮎(あゆ)、鯵(あじ)
秋ごろ
さつまいも、じゃがいも、ごぼう、米、栗、秋刀魚(さんま)、鮭(さけ)
冬ごろ
食べ物の栄養
食べ物には色々な栄養が含まれており、健康に生活するためにきちんと食事をとりましょう。
また、食べ物によって含まれる栄養は異なるので、野菜や肉など、色々な食材をバランスよく食べましょう。
栄養の種類と働き
食品に含まれている栄養素には、炭水化物、脂質、たんぱく質、無機質(ミネラル)、ビタミンがあり、これらの5つは五大栄養素と呼ばれています。
炭水化物
炭水化物は、糖質と食物繊維の総称です。
糖質にはブドウ糖(グルコース)やでんぷんといったものがあり、体の中でエネルギー源として使われます。ちなみにブドウ糖(でんぷんが体の中で分解されるとブドウ糖になります)は、脳の唯一のエネルギー源といわれています。
食物繊維は消化・吸収されませんが、腸の調子を整え便通を良くしたり、脂質の吸収を緩やかにしたりする働きがあります。
炭水化物は主にお米、パン、めん類などに含まれています。また食物繊維はひじきやごぼう、豆類やきのこ類などに多く含まれています。
脂質
脂質には、中性脂肪やコレステロールなどがあります。
脂質も体の中で、エネルギー源として使われます。そのほかにも、細胞膜やホルモンといった体の組織の成分になったり、体温の保持したり、脂溶性ビタミンといわれるビタミンAやビタミンDなどの吸収を助けたりする働きがあります。
脂質は多く取り過ぎると、肥満の原因になりますが、不足すると疲れやすくなったり、抵抗力が落ちたりするので、バランスよく取りましょう。
脂質は主に肉、魚、卵、乳製品などに含まれています。
たんぱく質
たんぱく質(プロテイン)は、20種類のアミノ酸で構成されており、コラーゲンやヘモグロビンなどがあります。
たんぱく質は、炭水化物や脂質と同じように、エネルギー源として使われます。また、筋肉、臓器、血液、皮膚、毛髪など、体を作る材料になります。
たんぱく質は主に肉、魚、卵、大豆などに含まれています。
無機質(ミネラル)
無機質(ミネラル)には、カルシウムやカリウム、鉄など様々なものがあり、体の中でつくることができないため、食べ物から取る必要があります。
無機質は種類によって働きが異なっており、骨や歯、血液を作るもとになったり、神経や筋肉の働きに関わったりしています。
無機質はお互いに影響し合う場合もあるので、バランスよく取るのが大切です。
ちなみに、給食でも出ている牛乳は、カルシウムが多く含まれているうえに、他の食品に比べてカルシウムの吸収率が高いといわれています。
| 無機質の名前 | 主な働き | 含まれる食べ物の例 |
| カルシウム | 骨や歯の材料になります | 牛乳、乳製品、骨ごと食べられる小魚、大豆製品など |
| カリウム | 細胞や神経などが正常に働けるようにしたり、塩分の取り過ぎを調整したりします | ひじき、昆布、野菜、果実類など |
| 鉄 | 体の中で酸素を運びます | レバー、豆類、海藻類など |
| 亜鉛 | 体の機能の維持や、細胞をつくる作用に関わっています | 牡蠣(かき)、赤身の肉、魚介類など |
上に挙げた以外にも様々な無機質があるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。
ビタミン
ビタミンには、ビタミンAやビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンCなど13種類ありますが、ほとんどは体の中でつくることができないため、食べ物から取る必要があります。
ビタミンは、種類によって働きが異なりますが、体の機能を正常に保つため必要な栄養素で、他の栄養素の働きを助けてくれます。
| ビタミンの名前 | 主な働き | 含まれる食べ物の例 |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜を健康に保ったり、病気などへの抵抗力を高めたりします。 | レバー、バター、卵など |
| ビタミンB1 (チアミン) |
糖質からエネルギーをつくるのを助けたり、神経の働きを助けたりします。 | 米ぬか、豚肉など |
| ビタミンB2 (リボフラビン) |
脂質をエネルギーにしたり、皮膚や髪などの細胞の再生に関わったりします。 | レバー、のり、魚介類など |
| ビタミンC | 体の中でコラーゲンをつくるのを助けたり、病気などへの抵抗力を高めたりします。 | アセロラ、赤ピーマン、かんきつ類など |
| ビタミンD | カルシウムやリンの吸収を助けます。 | 魚類、卵など |
上に挙げた以外にも様々なビタミンがあるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。
噛むことの大切さ
食べ物をよく噛んで食べることは、下に記載している誤嚥の防止につながるだけではなく、以下のような効果があると言われています。
- 口の中につば(唾液)が多く出て、食べ物からの栄養を多く取り入れることができます。また、つば(唾液)の抗菌作用によって、むし歯や口臭の予防につながります。
- たくさん噛むことで、満腹感を得られ、食べ過ぎを防ぐことができます。
- 食べ物が細かくなることで、胃や腸への負担を減らすことができます。
- 噛むことによって脳の血流が増加するので、脳の働きを活発にします。
- 歯と歯ぐきが丈夫になり、食べ物の味をおいしく感じることができます。
- 噛むことによって口の周りの筋肉が鍛えられ、はっきりとした発音につながります。また、全身の筋力も向上すると言われており、元気に活動することができます。
誤嚥の防止
日本では過去に、パンの早食いや、白玉団子やプラムをよく噛まずに飲み込んだことによる窒息事故が発生しています。特に、丸い形状の食材は、思いがけず飲み込んでしまう可能性があるので注意が必要です。
未然に誤嚥を防止するためのポイント
・食べ物は口に入れる前に、お箸等を使って食べやすい大きさに切りましょう。
・よく噛んで食べましょう。
・早食いをすると、食材を噛まずに飲み込んでしまうことがあります。早食いはやめましょう。
誤嚥が起きてしまったときの対処方法
1.背中を叩く(背部叩打法)

手のひらのつけ根で子どもの背中(左右の肩甲骨の中間あたり)を平手で何度も連続して叩きます。
2.腹部突き上げ法(ハイムリック法)

子どもの後ろから両腕を回し、みぞおちの下(へその少し上)で片方の手を握り拳にして、腹部を手前上方へ圧迫します。
【注意】腹部の内臓を痛める可能性があるため、腹部突き上げ法を実施した場合は、すみやかに病院を受診してください。
【注意】妊婦や乳児に対して「腹部突き上げ法」は行えませんので、「背部叩打法」のみ行ってください。
【参考】インターネットで「背部叩打法」や「腹部突き上げ法」と検索すると、動画を見ることができますので、参考にされてください。
食後の片づけ
食事が終わったら、食器等をきちんと洗って片付けることも大切です。
食中毒予防のために次のポイントに気を付けましょう。
-
ふきんは、煮沸消毒や台所用漂白剤につけるなどして、こまめに消毒しましょう。
-
包丁、食器、まな板等は、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒効果があります。
-
たわしやスポンジは、使用後はよくすすいでから、水気をよくきって乾燥させましょう。また、定期的に消毒しましょう。
また、食器の片づけなどはお子さんのお手伝いのチャンスでもあります。
食器を運ぶなど、少しずつでも家事を手伝ってもらいながら、コミュニケーションをとって、楽しみながら片付けをしましょう。
災害への備え
災害は突然発生します。家庭でも、いざというときに備えて準備をしておきましょう。
ここでは非常時のための食料への備蓄について紹介します。
非常時の食料
災害時の備えとして、
- 避難時にすぐに持ち出せる食料
- 道路の破損等により自宅で救助を待つときの食料
を用意しておくと安心です。
また、ガスなどが止まった場合に備えて、カセットコンロを用意しておくと料理の幅が広がります。
備えておく食料
家族の好みに合わせたものを準備しましょう。
すぐに持ち出せる食料としては、カンパンや缶詰など、火を通さずに食べられるもの。自宅で救助を待つときの食料としては、缶詰やレトルト・インスタント食品など、そのまま食べられるものや簡単な調理で食べられるものを準備しましょう。
災害時には不安やストレスで食欲がなくなってしまうこともあるので、食べなれたお菓子や甘いものがあると、心が落ち着きます。
備えておく量
目安としては、最低でも1人3日分、できれば1週間分の食料を、家族の人数分用意しておきましょう。また、飲料水は大人1人当たり、1日3リットルが目安といわれています。
ローリングストック
「ローリングストック」とは、
- 普段の食品や日用品を少し多めに買い置きし、
- 備蓄したもののうち、古いものから消費して、
- 消費した分を買い足す
という1から3を繰り返すことで、常に一定の量を保ちながら、備蓄品の「期限切れ」を防ぐ方法です。
災害への備えとして、ローリングストックをしてみましょう。
家庭備蓄ポータルについて
農林水産省のホームページでは、家庭備蓄に関する様々な情報を集約したポータルサイトを公開しています。
災害時の簡単レシピなども紹介されていますので、ぜひご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 教育庁 学校給食課
〒877-0078 大分県日田市大字友田1910番地10
電話番号:0973-23-5185(直通)
ファックス番号:0973-23-5186
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









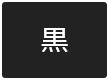
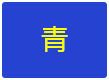
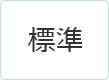


更新日:2025年03月19日