令和7年2月定例記者会見

令和7年2月の定例記者会見の内容、配布資料等は、下記からご覧ください。
動画配信
定例記者会見の動画を日田市公式動画チャンネル『Hita Tube』で配信しています。
2月の定例記者会見動画は、下記リンクをご確認ください。
配布資料
令和7年2月定例記者会見資料 (PDFファイル: 5.6MB)
関連リンク
国道386号 三郎丸橋被災に伴う、BRT臨時駅(バス停)の設置
会見録
【注意】市長、担当課及び記者等の発言内容については、単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上、作成しています。
市長あいさつ
おはようございます。今日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。
今日は案件がたくさんございますけれども、私からは2点申し上げます。
まず1つ目の住民の支え合いによる移動支援の取り組みでございます。運転免許返納後の移動について、市民の方から不安の声を多く聞いておりました。それで選挙のときにも、高齢者等の移動支援というのは公約の1つに掲げておりました。また市の調査でも、高齢者の3割が運転に不安があり、車を運転しない方の7割が日常生活に移動制約があると、いうような結果がございます。
またはそのすべてを公共交通でカバーすることは難しいので、住民の支え合いによる移動支援の実現ということで、今年度、住民向けにセミナー等を開催して参りました。今般、山田町で、第1号として、住民の支え合いによる移動支援が始まることになりました。それを1点目として、ご説明を申し上げます。他にも、いくつかの地域で実現に向けて取り組みを進めているところがございまして、これから広がっていくことを期待しております。高齢者等の移動支援に限らず、地域住民の支え合いで、地域の人と人のつながりが再構築され「支える・支えられる」そういう関係が循環する地域づくりが進むことも期待しているところでございます。詳しくは後で担当からご説明申し上げます。
次に2点目の日田市と日田市内高等学校等との包括連携協定締結式でございますけれども、包括連携協定、高校は県立だったり私立だったりするために、個別にはいろいろと連携しての取り組みがあったんですけども、市役所全体として、高校との連携の仕組みがありませんでしたので、今回協定を締結することにいたしました。先日、高校生との意見交換会でも、高校生の方から、「何が変わるのですか」というご質問があったんですけれども、例えばこれまでは、こういうことを頼みたいんだけど、市役所のどこに頼んだらいいんだろうとか、そもそもこんなことを頼んでいいんだろうかっていうようなことで、諦めてたこともあるんじゃないかと思いますけど、今後は、気軽に相談してもらえる窓口ができることで、連携の取り組みが広がることを期待していますというようなことを、お答えを申し上げました。これもまずは連携協定でその仕組みを作って、具体的にはまた意見交換等をしながら、高校とも相談しながら、1つ1つ取り組みを進めていきたいと思っております。これも詳しくは担当課から説明をさせます。私からは以上2点でございます。よろしくお願い申し上げます。
案件
住民の支え合いによる移動支援の取組が始まります(長寿福祉課)
○長寿福祉課長
長寿福祉課でございます。私からは、案件一番の住民の支え合いによる移動支援の取り組みについて説明させていただきます。会見資料の1ページをお願いいたします。
日田市では、今年度からNPO法人全国移動サービスネットワークと協働いたしまして、各地域で住民同士の支え合いによる、移動支援の仕組みづくりが進むよう取り組んで参りました。
この度、市内の山田町におきまして、この移動支援の取り組みが2月10日から開始される運びとなりました。
内容についてでございますが、実施主体は山田町自治会の『移動外出付き添い支援「とぎの会」』でございます。運行開始日は令和7年2月10日月曜日の予定となっております。当日は午前9時から、山田町公民館前におきまして出発式を行います。出発式には市長が出席をさせていただく予定でございます。支援の内容でございますが、現在行っております地域の方が週に1回山田町公民館に集まりまして、介護予防体操などを行う、「週一通いの場」への送迎や病院への付き添いなどの外出支援を行う予定としております。運転や付き添いをされる協力者につきましては、山田町の有償ボランティアの方々で、また、利用者につきましては、山田町にお住まいの65歳以上で、支援が必要な方としております。利用者が負担する利用料といたしましては、ガソリン代などの実費相当分としております。また、運行につきましては、予約の状況にもよりますが、毎日の運行を行い、朝8時から夕方5時まで、17時まで行う予定としております。主な利用ルートでございますが、利用者のご自宅から「週一通いの場」が行われる山田町公民館までや、地区の行事に参加される際のご自宅から朝日公民館までなどを予定しております。
なお、実施主体がこの事業を運営していくための財源といたしましては、介護保険制度を活用した補助や利用者からいただく、実費相当分の利用料などとなっております。私からの説明は以上でございます。
日田市と日田市内高等学校等との包括連携協定締結式について(企画課)
○企画課主幹
企画課でございます。私からは、日田市と市内高等学校等との包括連携協定の締結式についてご説明いたします。資料につきましては3ページから5ページとなっております。
日田市と日田市内の高等学校等が相互に連携協力していくために、包括連携協定を締結するもので、具体的には、若者世代が描く日田市の将来像を実現させるための意見集約や、地域探求を進めるための行政からの支援を恒常的な取り組みとし、イベント等の開催にあたっては、相互に連携することで、若者世代のまちづくりへの参画を促進していくことを目指しています。また、各学校が抱える課題の解決に向け、市としてサポートできるような仕組みづくりも考えていきます。
締結式の日時と場所につきましては、2月21日金曜日、午後3時45分から市役所7階の大会議室で行います。協定を締結する学校につきましては、日田高等学校、日田三隈高等学校、日田林工高等学校、日田支援学校、昭和学園高等学校、藤蔭高等学校の6校です。
締結式の出席者につきましては、学校からは、各校の校長、各校生徒は2~3人程度、日田市からは、市長、教育長です。なお、締結式の内容につきましては、現在最終調整中ですので、2月中旬ごろを改めてご連絡いたします。
このような協定締結は、大分県内で初の取り組みですので、締結式当日は、どうぞよろしくお願いいたします。以上で私からの説明を終わります。
済生会日田病院が設置する経営改善会議への参画について(健康保険課)
○健康保険課長
健康保険課です。よろしくお願いいたします。私からは、済生会日田病院が設置する経営改善会議への参画についてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。
済生会日田病院につきましては、厳しい経営状況が続いていることに加えて、医療を取り巻く環境が厳しさを増していることから、病院経営の健全化に向けた方針や具体的な取り組みなどを協議する経営改善会議を、済生会日田病院が令和7年4月に設置することとなりました。
この会議のメンバーの案といたしましては、病院経営の専門的な知見を持っておられる有識者や、地域医療構想や医療計画を策定する大分県、本市の地域医療に関わる日田市医師会、そして日田市などで構成する予定となっておりますが、引き続き調整を行って参ります。
この経営改善会議の役割といたしましては、令和7年度にコンサルタントを活用しながら、済生会日田病院の現状を把握するための経営分析を行い、それに基づいて、経営健全化の方針や具体的な対策を決定していくこととしております。決定した具体的な対策を確実に実行していける体制の構築を行うとともに、対策の進捗の管理を行うこととしております。今後は、済生会日田病院の経営に関することは、まずこの会議で協議いたしまして、必要に応じて理事会の了承を得ていくことになります。以上が済生会日田病院が設置します経営改善会議の説明です。
これからが、この経営改善会議に対する日田市としての関わりについての説明となります。
済生会日田病院は、日田市を含めた西部医療圏唯一の地域中核病院として重要な役割を担っておりまして、将来にわたって必要な医療を提供していただく必要があります。そのためには、経営の健全化が必須と考えております。これまで済生会日田病院と経営の健全化に向けて協議を進めてきた中で、日田市が病院経営に責任を持って関われる体制についても議論を行って参りました。その体制の1つとして、経営改善会議に西部医療圏の市町を代表しまして、日田市が参画することとしたものです。まずは、経営改善会議において経営の健全化方針などを検討するための支援を関係機関とともに行い、具体的な対策の実現に向けた支援につきましては、大分県などに働きかけるとともに、日田市としても行って参りたいと考えております。私からは以上でございます。
国道386号三郎丸橋被災に伴うBRT臨時駅(バス停)の設置について(地域振興課)
〇地域振興課長
地域振興課でございます。
私からは案件4、国道386号三郎丸橋被災に伴うBRT臨時駅(バス停)の設置について説明いたします。資料は7ページになりますのでよろしくお願いいたします。
現在、JR日田彦山線BRTひこぼしラインにつきましては、国道386号線の通行止めに伴いまして、市道北豆田三郎丸線を迂回路として運行している影響で、北友田駅、南友田駅のバス停には停車できない状況となっておりましたが、この度、臨時駅設置の手続きが整い、2月3日月曜日から臨時バス停の運用が開始されることとなりましたのでお知らせいたします。
設置場所につきましては資料の8ページ9ページをご覧ください。まず、北友田駅でございますが、駅は学校給食センターの前あたりになります。続きまして南友田駅でございますが国道386号線からニトリ方面の北側に向かっていきますと突き当たりまして、その突き当たりを120~130メーター、左に曲がっていただくと、南友田駅を新たに臨時駅として設置するということになっております。なお、仮設バス停は、2月2日に設置予定というふうにJR九州さんからお伺いをしているところでございます。私からは以上でございます。
質疑応答
〇記者
一番最初の移動支援について3点伺います。日田市の関わりですね、費用的な面で何かあるのかと、ないとしたら、どういう関わりがあるのかということと、あと移動支援についてはいろいろコミュニティバスとかデマンドタクシーとかいろんな制度をいろんなとこでやってるんですけども、これは多分その地元の有償ボランティアによるなんていうか送迎みたいな、コミュニティバスとか、デマンドタクシーとかそういう交通のくくりでいけば、何という名前のものになるのかということと、それは珍しいのか、県内とか、全国でやってやってるところはあるのかと、この3点をお願いします。
〇長寿福祉課長
市の関わりでございますけれども、まず財源的なものにつきましては、介護保険の制度を活用しました補助というところでございますけれども、それについては今、調整中でございます。それから、これまで行ってきた関わりについては、5月から市民セミナーなどを開催して、勉強会とか地域での懇談会などを行って参りまして、そして、この山田町におきましては、具体的な内容を、行政と、あと日田市社会福祉協議会、などと一緒に検討して参りました。
〇地域振興課長
地域振興課で公共交通の部分についてお答えさせていただきます。市内いろいろな公共交通、先ほどおっしゃいましたようにデマンドバス、デマンドタクシーや、いろんなバス、ひたはしり号なども走っておりますが、今回高齢者等の移動サービスで地域の方にやってもらうのはそこの隙間を埋める例えばひたはしり号でいけばバス停があるんですけど、やっぱ自宅からそのバス停まで何百メーターがあるともう歩けないとか、デマンドタクシーもあるんですけど一応公共交通ですので、公共交通をあくまでもつなぐところを運行してるいるので、それに該当しないところにはなかなか行けないような状態になっています。例えば、自宅から公民館っていうのがバス停とか公共交通をつなぐ場所ではないものですから、バス停とかがなければですね。ですからそういうところを地域の方に担っていただいて、高齢者の移動を支援していただけないかという取り組みを始めたものでございます。
位置づけについて詳細は担当総括から説明します。
〇地域振興課主幹
まず、運輸局に許可登録を要しない等とは、あくまでも住民が自主的にボランティアで行うという。今回有償ボランティアというところで仕組みが公共交通と違うという部分になります。
〇長寿福祉課長
続きまして県内の他市で行っている状況でございますが、先ほど申し上げました介護保険制度の補助を活用するというふうに説明させていただきましたけれども、そこで言いますと、国東市と別府市が取り組んでいるということは伺っております。以上でございます。
〇記者
介護保険の補助ということは利用者が出すということですし、結局市の手出しはないんでしょうかという、財政については質問と、いわゆる住民が有償ボランティアで、やるんですけども、そういう人を乗せる仕事じゃないから、多分許可がいらなくって、近所の人をどこかへ乗せてあげるっていうのの多分延長みたいなことじゃないかなあと思うんですけども、仕組みとしてはそういうことでよろしいのかということを聞きたいです。
〇長寿福祉課長
先ほどの介護保険制度につきましては、介護保険の特別会計の中を活用しておりますので、国のルールに基づきまして、国・県・市、それから市民の皆さんからいただく介護保険料、そういったものが財源というふうになっております。
〇記者
市の手出しは、あるんですか
〇長寿福祉課長
はい。市負担分もあります。
〇地域振興課長
先ほど、業として今してないんで近所の人がちょっと乗せていくという、それを仕組み化した形というふうに理解いただいて結構だと思います。
〇記者
さっきまず、国東と別府は、介護保険のこの日常生活支援総合事業を活用してやってるっておっしゃったんですが、これはいわゆる住民の支え合いによる移動支援をこの事業に適用してるっていう理解でいいんですか。
〇長寿福祉課長
昨年の4月に県が実施した調査によりますと、別府市も、国東市も日田市と同じような取り組みというところで住民の支え合いによる移動支援になっております。
〇記者
それと当然その事業を始められるということなので、それの収支っていうのも、想定を当然された上で始められるということになると思うんですが、どの利用者をどれぐらい想定をされて流量が実費相当分とありますけども、具体的にいくらとかその算定の根拠ですね、どうなってるのかっていうのを教えていただきたいというのと、あと今後の取り組み予定でいくつかの予定っていうのはあるんですが、具体的にいくつなんでしょうか。
〇長寿福祉課長
山田町が今設定しております、利用者からいただく利用料金、実費相当分になるんですけれども、地区内は100円いただくというところで、その中には、ガソリン代とか、あと保険料ですね。
そういったものが含まれております。一律で片道100円、ご自宅から、片道が100円ですね。ですので、先ほど申し上げました「週一通いの場」への送迎になりますと、往復で200円をいただくということになっております。利用者数については、今のところですね、利用者12名ぐらいいらっしゃるんではないかというところです。
〇記者
実際にその有償ボランティアで運転、付き添いをなさる方、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
〇長寿福祉課
いわゆる協力者につきましては、大体今のところ10名程度というふうに伺っております。
すいません。先ほどの利用料の件でございますけれども、運行に対して100円いただくようにはしておりますが、あと年間費としまして、今のところ年間1000円をいただくようなところで、設定をしているということでございます。
〇記者
他の地域でもいろいろ取り組みかけているところがある中でこの地域の、まず山田町の特徴っていうのがどんなところにあるのか、公共交通がどれくらい接続しているのかいないのかとかそういった特徴ですね、その中で呼びかけとしては昨年の6月とかでしたかね、5月6月に各地区でされて、山田町が実質的には一番最初に運行開始というふうなことになりました。この開始までこぎつけられた理由としては、行政としてはどういうふうなところにポイントがあったのかなというふうに感じてらっしゃるのかっていうふうなことと、あとすいません細かいところなんですけれども、先ほどの説明の中で地区内片道100円というふうにあったんですがこれは朝日地区というふうな理解でよろしいでしょうかというところをお願いします。
〇地域振興課長
山田地区にとって公共交通の部分お答えさせていただきます。山田地区にはひたはしり号のバス停は山田入口、朝日と山田の境ぐらいに、1つ設置しておりまして公共交通というものはそれひとつでございます。山田町の特徴とか、取り分けということではありませんが、こういう仕組みを作りたいという、地域の方の思いがやっぱ強く影響したんじゃないかなというふうに私は考えていまして、具体的に特殊で何が違うかっていうのはなかなか他の地域にもないので、やっぱり地域の主となって動いている方の、やっぱこれをやっていかないかん、地域は自分たちの地域は自分たちで住みよい地域に作っていかないといけないというような思いの強さが今回影響したんじゃないかなというふうに私は思っております。
〇長寿福祉課長
地区内といいますのは朝日地区内ということになっております。
すいません。それから先ほど読売新聞さんから聞かれました他の地区のことを聞かれてお答えしてないんですけれども、昨年5月から市民セミナーとかあと地域の懇談会などを行って参りましたけれども、そういったものを踏まえて、やはりいくつかの地域では、話し合いが今進められております。そして話し合いの中で、支援ニーズに関することですとか、あと住民向けのアンケートを実施するなどですね、それぞれの地区で取り組みに向けた検討が今進められているというものを承知しております。地区についてはちょっとまだ今のところは、決定はしていない状況でございます。
〇記者
その関連の質問なんですけれども2ページ目の2のところでですね、8月から9月ごろに市内6ヶ所で開催されたというのがあるんですがここは6ヶ所というのはどちらになりますかね。グループワークの方をされた場所についてです。
〇長寿福祉課長
地区は、前津江と三花、大山と天瀬で、天瀬が天瀬公民館と東渓分館の2ヶ所です。あと、アオーゼの6ヶ所で行っております。アオーゼで開催いたしましたのは、市内の中心部の方々を対象として行っております。
〇記者
それ以降は各地域によってちょっと進捗状況のばらつきはあるというふうな理解でよろしいですかね。
〇長寿福祉課長
はい。そうです。
〇記者
公共交通のある、なしというところ、山田町について教えていただいたんですけれども、これまで公共交通があそこは通ってなかったですかね大鶴から済生会病院まで行くバスが。かつて大鶴方面から済生会の方面まで路線バスが、ひたバスさんが走っていた時期がなかったかなと思うんですけれども。
〇地域振興課長
デマンドタクシーはあるんですけど、すいません、路線バスはもしかしたら私どもが把握しない前にあったのかもしれないですけど、すいません今そこの確認はとれません。
〇記者
現状なんですけれども、対象の方が65歳以上の支援が必要な方とあるんですけれども、例えば車椅子の方が利用できるのかとか現状をスタートしてこれからいろんな課題も拾い上げていくっていうことだとは思うんですが、利用者の対象としてはどういった方々になるんですかね。総合事業ってなると、ある程度こういった方っていうのができる表現できるかなと思うんですが。
〇長寿福祉課長
今この資料には、65歳以上の支援が必要な方と記載しておりますけれども、具体的にはですね、認定を受けてる要支援1と、2、あとチェックリストで対象となった事業対象者、介護認定を受けてる中では、比較的軽度な方が対象となります。
〇記者
これそもそもシステムとして、利用希望する方はどこに申し込みをして、サービスを具体的に提供するというのはどういう仕組みになってるんでしょうか。
〇長寿福祉課長
山田町が今回、チラシを作っておりまして、それを地域に今度まだ配布してないんですけど、もうこれから作り上げて配布する予定になっているようです。そしてその仕組みについてですけれども、事務局のボランティアさんがいらっしゃいまして、その人に利用したい方が連絡をして、依頼するといった、スタートはそのようになります。今のところは電話連絡というふうには想定をしております。
〇記者
もう1つだけ、今説明いただいた財源の部分でいわゆる公費は介護保険制度にあるこの事業を活用すると、そこから出る分だけってことなんですね。で、その予算的な手当っていうのは3月補正か何かにあるんでしょうか。
〇長寿福祉課長
出す補助金の分につきましては、今年度6年度当初予算で計上しておりますのでそれを、補正はなく活用できるものと考えております。
〇記者
国東と別府でっていうふうに介護保険を利用してというのは、おっしゃったんですが、中身の方を似てるんでしょうか。聞いてる範囲で結構ですが、ボランティアが、住民を買い物とか病院とか地区に連れていくと言う仕組みは同じといえるんでしょうか。
〇長寿福祉課長
大まかな仕組みについては山田町と同じような仕組みではございますけれども、その中で、利用料をいくらいただくとかそういったことについては、それぞれの団体が決めておりますので、様々だと思っております。
第42回天領日田おひなまつりの開催について(観光課)
〇観光課長
観光課でございます。資料の方10ページと別添のパンフレットをご覧ください。
それでは天領日田の春の訪れを満喫するイベントとして、「第42回天領ひたおひなまつり」についてご説明をいたします。
まず開催期間につきましては、2月15日土曜日から3月31日月曜日までの期間となります。会場につきましては、パンフレット2ページ3ページに記載しておりますが、全体で17施設で展示を行いまして、豆田地区で10施設、隈地区で5施設の他、有田地区で1施設、朝日地区1施設で展示がされます。
次に、期間中のイベントにつきましては、パンフレットの4ページ5ページに記載しておりますように、今回多くのイベントが開催されます。その中で主なイベントは、まず1点目が「青い目の人形パレード」を2月12日土曜日、午前10時30分からJR日田駅前で行います。次に「豆田流しびな」の体験を3月2日日曜日、午前10時から午後2時で桂林荘公園で開催します。また和の文化を楽しむことができる「懐かしの着物展」を3月1日土曜日から20日木曜日祝日の期間で、豆田まちづくり歴史交流館の旧船津歯科で開催をいたします。着物姿で町並み散策を楽しむことができます「レンタル着物の着付け」を3月1日から16日までの期間の土曜日、日曜日、豆田まちづくり歴史交流会横の離れ座敷で開催します。また今年卒業される高校生を対象に、無料で着物着付け等が体験できる「ふるさと思い出プロジェクト」を、3月4日火曜日、11日火曜日の2日間で、市内5つの高校の高校生30名を対象に実施いたします。
また今回から新しい取り組みとなりますが、中学校へ進学する児童を対象に、「古来より13歳は、節目とされ知恵もらいのお祝いをする習わし」に従いまして、「日田咸宜園十三歳祝いの会」を行います。開催日時は3月30日日曜日、13時から15時、咸宜園にて、小学校卒業生の30名を対象に実施いたします。
次に交通規制についてご説明いたします。こちらについてはパンフレットの7ページにありますように、2月22日土曜日から3月20日木曜日祝日の間の、土日、祝日、振替休日の10日間、午前10時から午後10時の時間帯で豆田地区で一方通行を行います。
最後になりますが、天領日田おひなまつりの期間中は、たくさんのイベントが開催されますので、ぜひ、天領日田の春の訪れを満喫ください。私からは以上でございます。
第45回日田大山梅まつりの開催について(大山振興局)
〇大山振興局長
大山振興局です。11ページをご覧ください。「第45回日田おおやま梅まつり」のお知らせです。
大山まつり実行委員会の主催で、2月16日日曜日から3月16日日曜日までの約1ヶ月間、日田おおやま梅まつりを開催いたします。会場につきましては、おおくぼ台梅園とふるや台梅園になります。なお、まつり期間中のイベント日については、おおくぼ台梅園が3月2日日曜日、ふるや台梅園が3月9日日曜日としております。おおくぼ台梅園のイベント内容といたしましては、豊作祈願祭における神事、献梅、玉串奉奠、式典、地元の学校等によるステージイベントなどを予定しております。ふるや台梅園のイベントにつきましては、地元自治会の主導で内容を決定して執り行われます。
その他の協力イベントといたしまして、株式会社おおやま夢工房によります。盆梅の展示、梅こぶ茶の振る舞い、様々なご試食の提供など、梅酒蔵おおやま、道の駅水辺の郷おおやまを会場に行われます。
また、大山ダムでは、まつり期間中の土日、祝日の日没後、水資源機構によります、大山ダム堤体のライトアップが行われます。梅まつりの説明は以上です。
令和6年度「咸宜園の日」記念事業及び関連事業について(咸宜園教育研究センター)
〇咸宜園教育センター所長
咸宜園教育研究センターでございます。お手元の資料では13ページから15ページとなります。
日田市では、廣瀬淡窓が、現在の地に咸宜園を開いた2月23日を「咸宜園の日」と制定しており、平成23年度から毎年「咸宜園の日記念事業」として、講演会などを実施しております。今年度も2月23日日曜祝日、パトリア日田小ホールにおいて、記念講演会と研究奨励事業の研究報告を実施いたします。
最初に豆田地区振興協議会主催の「咸宜園 世界遺産登録推進 小学生作文コンクール」において、今年度最優秀賞を受賞した作品の発表を行います。発表者は桂林小学校6年生、井上木詠(きえ)さんです。次に、記念講演会では、熊本大学永青文庫研究センター准教授の今村直樹先生に「明治維新史のなかの北里柴三郎」と題してご講演をいただきます。昨年7月から新しい紙幣が発行されましたが、千円札の肖像は、熊本県小国町出身の北里柴三郎に変わりました。実はその柴三郎が青年期に漢学などを学んだ人物は咸宜園の門下生でした。講演では、豊後・肥後の地域史を踏まえながら、明治維新という大きな変革の中に、柴三郎の青年時代を位置付けていただく予定です。
続いて咸宜園教育研究センター研究奨励事業の研究報告を行います。この事業は、咸宜園に関する調査研究を行う若手研究者を育成し、日田市が研究委託契約を結び、その成果を市民の皆様に報告するものです。今年度事業の採択を受けた、國學院大学大学院の布川寛大(かんた)さんから、「近世後期の大阪における咸宜園教育の展開-長府藩在村医古谷道庵の大坂遊学を中心に-」というテーマで報告をいただきます。現在の山口県出身の咸宜園門下生古谷道庵が、咸宜園の塾長を務めた広瀬旭荘が大坂に開いた塾で学んでおり、大坂旭荘塾の様子を古谷道庵の残した日記などを通じて研究したものです。
次に「咸宜園の日」関連事業をお知らせします。1つ目は、「淡窓先生に学ぶ~学校の取り組み~」展示です。市内の各小中学校で取り組んだ咸宜園等に関する学習成果を展示するものです。展示期間は、令和7年2月7日金曜日から2月20日木曜日までです。会場は日田市複合文化施設アオーゼ1階多目的ホールです。今年も昨年度に引き続き、市内の小中学校全30校から出展があります。
最後に咸宜園教育研究センター春季企画展のお知らせです。咸宜園教育研究センターでは、市民や門下生の子孫の方から、廣瀬淡窓をはじめ、咸宜園の歴代塾主や、門下生に関する資料について、寄贈・寄託の申し出を受けて、随時受け入れております。これらの資料については、毎年の春季企画展において、新収蔵品展として展示をしております。今回は、咸宜園第3代塾主の廣瀬青邨の成果に残された掛け軸を中心に展示をしております。開催期間は4月15日火曜日までです。
咸宜園教育研究センターは通常水曜日が休館ですが、天領日田ひなまつり期間中は休館せずに開館いたしております。皆様のお越しをお待ちしております。本日発表の詳細につきましては、15ページのチラシをご覧いただきたいと思います。咸宜園教育研究センターからのお知らせは以上でございます。説明は以上となります。
令和7年2月行事予定(総務課)
8番の令和7年2月の行事予定表は、資料最後の予定表をご確認ください。
質疑応答
〇記者
すいません、咸宜園のことなんですけれども、北里柴三郎さんが学んだ門下生ってのはどなたなんでしょうか。
〇咸宜園教育研究センター所長
廣瀬淡窓に学んだ、園田鷹巣という人物で、お隣り玖珠町、久留島藩(森藩)の儒学者でありました。柴三郎のお母さんはもともと玖珠の出身だということもあって、玖珠町の方に学びに行ったというのが青年時代だそうです。
〇記者
すいません。済生会のこととBRTのことについて再度お願いします。
済生会日田病院のことなんですけれども、厳しい経営状況かというふうにあるんですが具体的にはどういった状況になっているのか、この経営改善会議というふうなものの中に日田市も入っていくというふうなことなんですけれども、今後、日田市が公金を出すようなことも想定されているのかどうなのかっていうなところを教えてください。
〇健康保険課長
それではまず経営状況についてですが、具体的なですね金額等についてはここで差し控えさせていただきますが、市が確認している中で言いますと、今年度、決算書類等の提出がありました。
それを見ますと、平成28年度以降、コロナ対策の補助金を受けた令和2年から令和4年度の3年度除き、慢性的な赤字経営の状態が続いていることはわかっております。現在、赤字解消に向けて明確な対策が、見いだせないというふうな状況というふうなことも思われますので、ですからこれ、今後コンサルを活用しながら、有識者の助言を受けて、当然やり方によっては黒字化が見込める診療科もある、あるでしょうし、市内の別の医療機関に任せてもいい分野もあるでしょうし、どうしても黒字化が見込めない、しかし、この西部医療圏に必要な部分もあるでしょうからそういったものについて、この経営改善で、つまびらかにしていきたいと考えております。
市の公金の投入ということなんですが、具体的な対策に向けた支援というのは、先ほど言いましたように、経営改善会議で諮っていきますのでその後、必要なものについては、当然県や構成市町村、構成団体も含めてですね、協議して参りたいと考えています。
〇記者
会議の中でしっかりと課題を明確にした後、必要性があれば、早々の対応というふうなことは、また考えていないわけではないというふうな形でしょうか。
〇健康保険課長
そうですね将来的に向けて、そういった必要であるということがわかり次第、そういった手当というか、支援というのは考えております。
〇市長
現在でも基準に沿って、3600万円支援しております。
〇記者
あとこの説明資料の中で西部医療圏の市町を代表してという表現があるんですが、玖珠町・九重町との連携というふうなことを、この辺りも救急搬送を含めていろいろな課題があるのかなと思うんですが、そこは日田市と玖珠・九重の両町とも協議っていうのは現状というふうにされてるんでしょうか。
〇健康保険課長
これまでも西部医療圏での構成団体として両町には、必要に応じて説明や協議を行って参りました。その中でこれまでの経緯や今後の進め方につきましては賛同を得ております。経営改善会議についても、より実行性の高い会議体として、人数も可能な限り少数でという意見もありましたので、構成市町の代表として、ある程度姿が見えてくるまでは、日田市が代表して実行していくことを事も了承していただいておりますので、その中ででも両町からは、必要に応じて報告や協議の場の設定などの要望というのはいただいておりますので、状況を見ながら適宜対応して参りたいと考えております。
〇記者
今回のこの経営改善会議の経営上の位置付けについてもう少し詳しく教えていただきたいんですけれども、済生会が立ち上がったところからの経緯があってっていうふうなところもあって、当時は日田市も経営の方に参画していたというふうな経緯が当時はあったかと思います。その中で、日田市だったり、市の職員というふうなものが、理事の中に入れない定款か何かの中にそういった記載があるようで、そこで今回もこういった会議の発足をというふうな流れなんだろうなというふうに理解してるんですけれども、そうなったときに、経営的なことも必要に応じて理事会の承認を得ることとするというふうなことがあるんですけれども、このあたりについては済生会の方はその定款運用上とか、経営の運営上とかっていうふうなところで、クリアしているというふうな認識でいいのかどうなのかっていうところをそういう意味での位置付けを教えてください。
〇健康保険課主幹
今、問い合わせの件は済生会日田病院側の話にはなるんですが、この経営会議の中で、経営に関することはまずこちらで協議をする、こちらで一定の方針を決めるというところのようですので、その決めたものについて、当然全体の組織の決定としてはやはり理事会での決定という形になりますので、ここで決まった内容を理事会の方に上げて、承認いただいて、意思決定がなされそれが実行されていくという形になろうかと思います。
〇記者
済生会日田病院としてもこの会議体については、しっかりと存在感と、存在意義と、そういったところについては認識していただいてるというふうな位置付けでよろしいですよね。
〇健康保険主幹
その通りです。先ほど記者さんの方からも紹介ありました通り、こちらについては済生会日田病院さんと協議して最終的にできてきた形と、本来であれば、経営に関与する形になるだろうかという話をお話した中で、今紹介がありました通りどうしても理事の方には、行政側が入れないということなので、こういった、会議体で議論したらいかがでしょうかという話を受けまして、こういった形になっております。
〇記者
市長にお伺いしたいんですけれども、こういった形でしっかりとした市の課題感を相手方に伝えていくというふうなことだと思います。現状その済生会が抱えている課題、経営上の部分も含めてなんですけれども、医療的なサービスっていう点で、例えば小児科だったり、産科だったり、そういったところを以前会見でも質問させていただきましたけれども、市として現在大きな課題を抱えている状況があります。ここに対しては今回の経営に対して、しっかりと意見を出していくっていうふうな方向性について言えば、今後どういった課題が相手方のこの経営の中で、俎上に上がってくると考えてらっしゃいますか。
〇市長
経営をどう改善していくかという中に、今医師や看護師を十分確保できないという問題もありますから、どういう診療科は残さなければいけないか。さっきちょっと課長も申し上げましたが、こういう診療科については、県内の他の医療機関にお願いできるかとか、三次救急みたいなものは、現在でも西部医療圏の外にお願いしてますけども、あと日田市の場合は久留米大との関係もございます。
そういう全体の中で、産科それから小児科についての課題は認識しておりますので、全体の中で、どう対応していくかというのは、これから有識者の意見もいただきながら考えていきたいと思っております。
〇記者
あと1点、コンサルタントも活用しながらという表現があるんですがこの日田市が採用するだとか日田市が委託するとかっていうふうなことではなくて、ここはもう、経営体の方がコンサルタントなどを活用しながらやっていただくというふうなことですかね。
〇健康保険主幹
その通りです。済生会さん側がということです。
〇記者
それからあとBRTの方なんですけれども、今回バス停が設置されるというふうなことなんですが、これまでの経緯について教えてください。日田市の方からいつ頃例えば設置してくれというふうな要望出したらとか、地元の方は早い段階からですね、取材でも聞いてたんですけれども、そのタイミング等々について教えてください。
〇地域振興課長
すいません、今詳細な資料を持っていないので記憶の中でお答えさせていただきますけど、まず被災して、要望書というのは正式に上がってきていないんですけど、北友田三丁目の自治会から口頭で「作っていただけるとありがたいな」というふうにいただきました。その周辺の地域の自治会長のところに「不便はないですか」とトータル的な意見聴取に回った経緯はございます。
そしてJRさんと仮設バス停の設置については、確か10月だったと思うんですけど、設置ができないかということで協議をさせていただきました。そしてその中でいろんな意見出たんですけど、JRさんとしては今あるバス停を基本的にはもう市道側に移すところで、今迂回路となって交通量も多いですから、今通ってる交通の支障にならないところに設置したいということで協議が整いまして、今回、運輸局の正式に許可が出たという形でございます。すいません、一回目は7月31日に協議しています。そしてそのあと10月です。
〇記者
このバス停の設置っていうのはもう、動かすだけとはいえ、運輸局の許可が必要なんですね。わかりました。あと、南友田駅の方なんですけど、片側通行になってるところから離れたところですかね。
何か目標になるものが多分何もないってことだと思うんですけど。
〇地域振興課長
国道からニトリの方に曲がるとTの字ですよね。そして、左側に行くとですね右側の方がちょっと広くなってます。防火水槽やごみ置き場があるんですが、そのへんです。
〇記者
片側通行からとかちょっと離れたところということですね。
〇地域振興課長
そうです。
〇進行
それでは定刻となっておりますので、以上をもちまして、令和7年2月の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市総務企画部 企画課 広報・広聴係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8627(直通)
ファックス番号:0973-22-8324
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









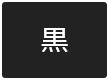
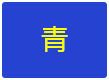
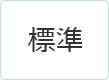
更新日:2025年02月18日