定期予防接種の種類と実施方法
子どもの予防接種
定期予防接種である五種混合、麻しん(はしか)・風しん混合、日本脳炎、BCGなどの予防接種を、病院や診療所等で個別接種方式で実施します。
予防接種は、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種時期などが定められています。詳しくは、下記の表をご参照ください。
予防接種を受ける際には、必ず事前に医療機関へ予約し、「母子健康手帳」を持って受診しましょう。
【定期予防接種実施医療機関】
予防接種の対象者(接種時期)
【乳幼児を対象に行う予防接種】
接種は標準的な接種年齢の期間に行うことをお勧めします。
| 種類 |
法で定められた対象年齢 (無料で受けられる年齢) |
接種回数 | 標準的な接種年齢 | 接種間隔 | 他の種類のワクチンが接種できるまでの間隔 | |
|
五種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ混合) |
1期 |
生後2か月以上7歳6か月未満 |
初回3回 |
生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 |
20日から56日までの間隔 | 制限なし |
| 追加1回 |
初回接種終了後、6か月から18か月までの間 |
― | ||||
|
四種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ混合) |
1期 |
生後2か月以上7歳6か月未満 |
初回3回 |
生後2か月以上1歳未満の間 |
20日以上、標準的には20日から56日までの間隔 | 制限なし |
| 追加1回 |
初回接種終了後、12か月以上18か月未満の間 |
― | ||||
|
麻しん・風しん混合 (MR) |
1期 | 1歳以上2歳未満 | 1回 | 早期の接種機会を確保すること | ― |
【注意】次に”注射生ワクチン”を接種する場合は27日以上 【注意】その他のワクチンは制限なし |
| 2期 | 5歳以上7歳未満で、小学校入学前の一年間。(いわゆる、年長児の期間) | 1回 | 早期の接種機会を確保すること | ― | ||
| 日本脳炎 | 1期 | 生後6か月以上7歳6か月未満 | 初回2回 | 3歳以上4歳未満の間 | 6日以上、標準的には6日から28日までの間隔 | 制限なし |
| 追加1回 | 4歳以上5歳未満の間(1期初回終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年置く) | ― | ||||
|
BCG (結核予防) |
1歳未満 | 1回 | 生後5か月以上生後8か月未満の間 | ― |
【注意】次に”注射生ワクチン”を接種する場合は27日以上 【注意】その他のワクチンは制限なし |
|
| ヒブ | 生後2か月以上5歳未満 | 詳細は下記のとおり | 制限なし | |||
| 小児用肺炎球菌(15価、20価) | 生後2か月以上5歳未満 | 制限なし | ||||
|
水痘 (水ぼうそう) |
1歳以上3歳未満 | 初回1回 | 1歳以上1歳3か月未満の間 | ― |
【注意】次に”注射生ワクチン”を接種する場合は27日以上 【注意】その他のワクチンは制限なし |
|
| 追加1回 | 初回接種終了後3か月以上(標準的には初回接種終了後6か月から12か月未満の間) | ― | ||||
| B型肝炎 | 1歳未満 | 3回 | 生後2か月以上、生後9か月未満の間 | ― | 制限なし | |
| 1回目接種終了後27日以上 | ||||||
| 1回目接種終了後139日以上 | ||||||
| ロタウイルス感染症 | 1価ワクチン | 出生6週0日後から出生24週0日後まで | 2回 | 1回目の接種は、生後2か月に至った日から出生14週6日後まで | 前回の同一ワクチン終了後27日以上 | 制限なし |
| 5価ワクチン | 出生6週0日後から出生32週0日後まで | 3回 | ||||
◎令和6年4月1日から、五種混合ワクチンが追加されました。
◎令和6年4月1日から、小児用肺炎球菌ワクチン沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンが 追加されました。
◎令和6年10月1日から、小児用肺炎球菌ワクチン沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンが 追加されました。
【異なるワクチンの接種間隔の一部緩和について】
- 令和2年10月1日から、異なるワクチンを接種する場合の接種間隔の一部が緩和されました。
- ただし、注射生ワクチンの接種後に、異なる種類の注射生ワクチンを接種する場合は、これまでどおり27日以上の間隔をあける必要があります。
- 特に医師が認めた場合は、同時接種を行うことができます。
- 小児用肺炎球菌や日本脳炎などの同一ワクチンを複数回接種する必要がある場合は、ワクチンごとに規定されている接種間隔に従ってください。
- 接種後数日は接種部位の腫れなどの症状が出る場合がありますので、接種間隔については医療機関へご相談ください。
ヒブ
| 初回接種開始 | 接種回数 | 接種間隔 |
| 生後2か月以上生後7か月未満の間(標準) | 初回3回 | 27日以上、標準的には27日から56日までの間隔 【注意】初回の2回目及び3回目は1歳未満までに行うこと。 |
| 追加1回 | 初回3回目接種終了後7か月以上、標準的には7か月から13か月までの間 | |
| 生後7か月以上1歳未満の間 | 初回2回 | 27日以上、標準的には27日から56日までの間隔 【注意】初回の2回目は生後1歳未満までに行うこと。 |
| 追加1回 | 初回2回目接種終了後7か月以上、標準的には7か月から13か月までの間 | |
| 1歳以上5歳未満の間 | 1回 | ― |
小児用肺炎球菌
| 初回接種開始 | 接種回数 | 接種間隔 |
| 生後2か月から生後7か月未満の間(標準) | 初回3回 | 27日以上、標準的には1歳未満までに27日以上の間隔 【注意】初回の2回目及び3回目は2歳未満までに行うこと。 |
| 追加1回 | 1歳以降に、初回3回目接種終了後60日以上 (標準的には1歳以上1歳3か月未満の間) |
|
| 生後7か月以上1歳未満の間 | 初回2回 | 標準的には1歳未満までに27日以上の間隔 【注意】初回の2回目は2歳未満までに行うこと。 |
| 追加1回 | 1歳以降に、初回2回目接種終了後60日以上 | |
| 1歳以上2歳未満の間 | 2回 | 60日以上 |
|
2歳以上5歳未満の間 |
1回 | ― |
【小学生を対象に行う予防接種】
| 種類 |
法で定められた対象年齢 |
接種回数 | 標準的な接種年齢 | |
|
二種混合 |
2期 | 11歳以上13歳未満の者 | 1回 | 11歳以上12歳未満 |
| 日本脳炎 | 2期 | 9歳以上13歳未満の者 | 1回 | 9歳以上10歳未満 |
【中学生・高校生を対象に行う予防接種】
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチン接種
令和3年11月26日付で厚生労働省からの通知により、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンの定期接種の積極的な勧奨の差し控えが廃止されました。
| 対象年齢等 | 標準的な接種期間 | ワクチンの種類 | 回数 | 接種間隔 | ||
| 小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性 | 中学1年生相当の年齢の間 | 2価 | 3回 |
2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 1か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種を行う。 |
||
| 4価 |
2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種を行う。 |
|||||
|
9価 |
15歳未満で1回目を接種 | 2回 |
5か月以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 6か月の間隔をおいて接種 《注意》5か月未満で2回目を接種した場合は、9価ワクチン3回接種の接種間隔で合計3回接種する。(下欄を参照) |
|||
| 15歳以上で1回目を接種 | 3回 |
2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種を行う。 |
||||
◎令和5年4月から、9価HPVワクチンが定期接種で使用することができるようになりました。
ヒトパピローマウイルス感染症関連リンク
日本脳炎の特例措置について
平成17年度から平成21年度までの間、積極的な接種勧奨を差し控えたことによって日本脳炎の予防接種が終了していない次の人は、未接種分を定期接種として無料で実施できます。
【平成19年4月1日以前生まれで20歳未満の人】
全4回接種(1期初回1回目、2回目、1期追加、2期)のうち、不足している回数を、20歳の誕生日の前日までの間に定期接種として接種できます。
接種回数と間隔
◆全く接種したことがない場合
第1期初回接種:6日以上(標準的には6日~28日まで)の間隔をおいて2回接種
追加接種:初回接種終了後6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおいて1回接種
第2期:第1期追加接種終了後、6日以上の間隔をおいて1回接種
◆1回でも接種している場合
6日以上の間隔をおいて、残りの回数を接種
(ただし、接種を始める場合は、既に接種済みのものから6日以上の間隔をあけること)
日本脳炎関連リンク
予防接種による健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、日田市健康保険課保健医療係にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳細は下記ページをご確認ください
定期予防接種を大分県外で受ける場合
定期予防接種を大分県外で受ける場合は、事前に予防接種実施依頼書を発行する手続きが必要になります。
接種費用は一旦、自己負担をしていただきますが、後日償還払いにて助成します。
予防接種済証の交付について
母子健康手帳を紛失した等の理由で予防接種の履歴を知りたい場合、本市が把握する予防接種履歴を『予防接種済証』として、健康保険課保健医療係の下記窓口で交付を申し込むことができます。
【申請に必要なもの】
(1)予防接種済証交付申請書(健康保険課保健医療係窓口、ホームページからダウンロード)
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【注意】電話での接種履歴確認の問い合わせには対応できません。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 感染症対策係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(日田市役所6階)
電話番号:0973-22-8243(直通)
ファックス番号:0973-22-8315
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。









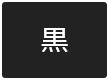
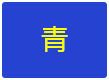
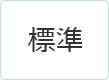
更新日:2025年04月01日